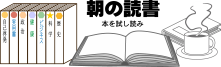※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
湿原が世界を救う
水と炭素の巨大貯蔵庫
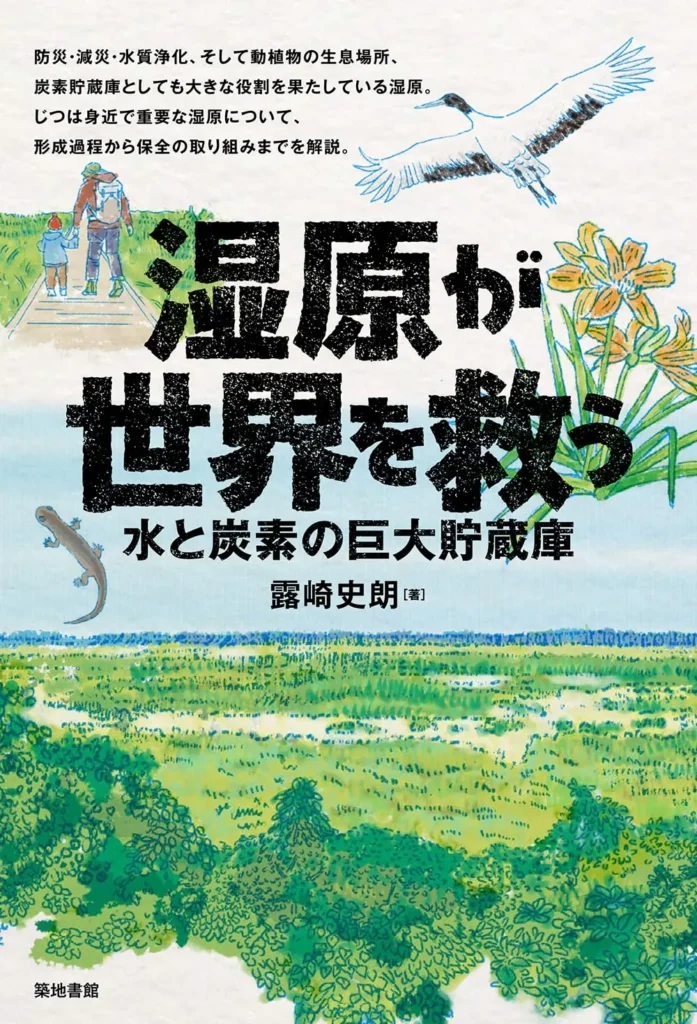
露崎史郎
植物生態学、環境保全学を専門にしている。
日本植物学会奨励賞、日本生態学会功労賞などを受賞。
菊地書館株式会社
- 序章
- 人間と湿原の歴史
- 湿原と友達になろう
- ところ変われば湿原も変わる水たまりだって湿原
- 湿原の範囲を決めておこう
- 湿原は水を抜きには語れない
- 冷温帯の湿原は泥炭を抜きには語れない
- 湿原の植物
- 湿原が地域と世界のあり方を決める
- 誰がために泥炭は消える
- 誰がために湿原を保全・復元するのか
- 〈コラム1〉湿原研究のきっかけ
- 第1章 湿原の生態系と景観
- ヨシスゲ湿原
- ミズゴケ湿原
- 同情するなら水をくれ
- 地形学・ 地理学での湿原分類
- 統一見解はなくても湿原は存在する
- 湿原生態系と湿原景観
- 湿原は里山景観の必須アイテム
- 北海道に里山はあるのか
- 北海道的里山
- アイヌ的里山
- 〈コラム2〉 セントヘレンズ山の湿原
- 第2章 湿原の機能 行きつく先は地球温暖化
- 湿原の物理的・化学的・生物学的機能
- 生態系サービス モネの「睡蓮の池」
- 冷温帯に泥炭湿原は多い
- 湿原の泥炭は炭素の膨大な貯蔵源
- 生産力を知ることは炭素固定量を知ること
- 残された湿原
- 熱帯泥炭
- 地球温暖化を加速する正のフィード
- 湿原とメタンとCO2
- 〈コラム3〉 シベリア・アラスカのツンドラ調査
- 第3章 湿原の遷移
- 遷移
- 極相 森林化とミズゴケ湿原化
- 攪乱泥炭採掘地を例に
- 地下部探検隊
- 日本は火山大国湿原にも影響するのか
- 永久凍土と湿原
- タイガもツンドラもミズゴケが大事 森林火災とツンドラ火災
- 森林火災後の遷移
- 〈コラム4〉 野外調査では何があっても動じない
- 第4章 湿原の保全
- 湿原保全に必要なツール生活史を知ること 生活史を知ること
- 種子散布 植物が長距離移動できるのは種子の時だけ
- 埋土種子
- 成長・死亡
- 開花結実
- タイガ・ツンドラ・泥炭地
- 〈コラム5〉西オーストラリアにて
- 種間競争と定着促進効果
- 食物網
- 鍵種と傘種
- 第5章 湿原の復元
- 「保全から復元」への考え方を確認
- 攪乱維持型の湿性植生
- 湿原の乾燥化 湿原の保全・復元の始まり
- 生物多様性
- 緩衝帯 (バッファ ゾーン)
- 回廊(コリドー)
- 地形的多様性谷地坊主って何?
- 押し出し効果絶滅危惧種の保全
- 復元の実践
- 〈コラム6〉ある調査中の出来事
- 第6章 日本の湿原(サロベツ原泥炭採掘跡地)
- サロベツ湿原とは
- サロベツ湿原の歴史
- 復元成果の評価
- サロベツ泥炭採掘跡地の遷移
- サロベツでもここまでは行けるかも
- 動物も菌類も遷移する
- 撹乱と中規模攪乱仮説
- 〈コラム7〉日本(北海道)の湿原
- 第7章 湿原の過去・現在・未来
- 冷温帯域湿原における復元実験
- 保全・復元の評価ができないと未来はつくれない
- スケール依存性要因
- 自然との共存・共生
- 再生可能エネルギー(再エネ)との両立
- 自然再生の最終兵器 ビオトープ
- 持続可能性と湿原
- 環境教育(湿原の未来を見守るために)
- 〈コラム8〉 湿原の過去・現在・未来
- 終章 湿原の豊かさを守る
- 生態学の応用だけでは保全・復元はできない
- 環境科学・地球環境科学の
- 必要性 /江戸の環境科学
- SDGsと湿原
- 湿原再生の市民科学
- SDGsを超えて(ポストSDGs)
- 最後の最後に 湿原オンリーも困るが
- 〈コラム9〉 再生可能エネルギーと環境保全の両立
- おわりに
書籍紹介
この本は、湿原という一見地味に思える自然環境が、実は地球の未来を左右する重要な役割を担っていることを、わかりやすく、かつ情熱的に教えてくれます。露崎さんは、北海道大学で植物学を専門とする研究者で、湿原の生態系やその保全について長年研究を重ねてきた方です。その深い知識と愛情が、ページの随所に感じられる作品となっています。
湿原が単なる水たまりや泥の土地ではなく、多様な動植物を育む命のゆりかごであると同時に、水と炭素を大量に蓄える「貯蔵庫」としての役割が丁寧に描かれています。湿原は、洪水を防ぐ保水機能を持ち、泥炭として膨大な炭素を閉じ込めることで気候変動の緩和に貢献します。こうした機能は、現代の環境問題を考える上で非常に重要です。露崎さんは、湿原がどのように形成され、どんな生き物がそこに息づいているのかを、専門的な内容を初心者にもわかるように解説しています。特に、湿原特有の植物や動物たちの暮らしぶりは、まるで小さな宇宙を覗いているようなわくわく感を与えてくれます。
開発や気候変動による影響で、世界中の湿原が失われつつある現状を、露崎さんは憂いながらも希望を持って語ります。湿原の保全や復元の取り組みが具体的に紹介されており、読者として自分に何ができるかを考えるきっかけになります。たとえば、湿原の保護活動に参加したり、環境に配慮した生活を心がけたりと、小さな行動が大きな変化につながることを示唆しています。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
生態系サービス

北海道では、針広混交林という独特な森林が見られます。その植生と地域の関係はアラスカに似ているのです。
生態系サービスとは、生態系を構成する種の高い多様性を維持することでヒトが得られる利得を意味します。湿原がヒトにもたらす利得は、わかりやすいところで泥炭蓄積です。泥炭は多量の炭素を貯留しています。
泥炭は燃料として利用できるため、アラスカのクロトウヒ林ではミズゴケの林床がエネルギー源となっています。泥炭地は火災と隣り合わせであり、この地域と火災は切っても切れない関係があります。
泥炭地保全や復元の必要性は、吸収する炭素の量より二酸化炭素が放出量が多くなってしまうと、生態系などの環境問題につながるというわけです。