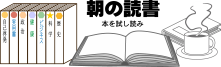※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
この不平等な世界で、僕たちがスタートラインに立つために
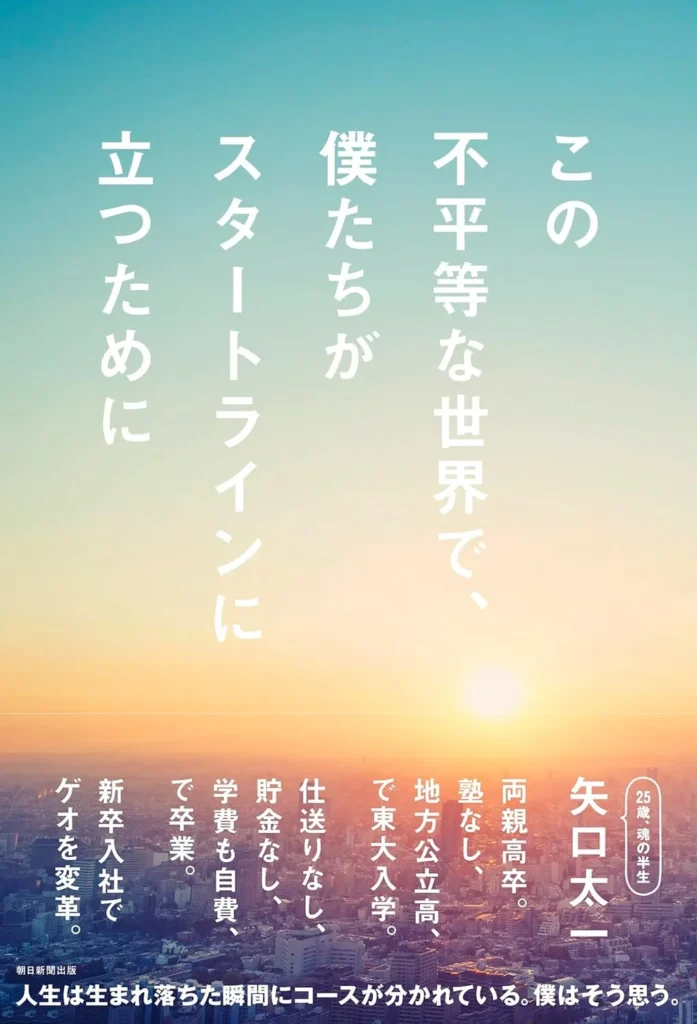
矢口太一
霞ヶ関キャピタル株式会社AI Lab シニアストラテジスト
東京大学大学院新領域創成科学研究科 在学中。
朝日新聞出版
- プロローグ スタートラインに立つために
- 1章 「東大なんか行けるはずがない」と先生は言った
- 田舎の少年
- セミとの出会い
- 科学賞
- セミの秘密
- 陸上大会
- 東京大学に行くぞ!
- 平凡な成績
- 可能性はあるか?
- 夏はセミをやる
- 「東大なんか行けるはずがない」
- 「常識」は抜け駆けを許さない
- 中2の夏
- セミが飛ぶのを撮ってみよう
- 本と父
- 三重県展最優秀賞!
- 選外
- 世界大会に行きたい!
- 疲労骨折
- 中3の夏
- 東海大会
- 建白書を書く
- 陸上部引退
- 100mとセミ
- 全国展入選
- 東京の舞台
- 大学教授
- 「それでええんか?」
- 「知事に会いたいです!」
- 表敬訪問
- 御守り
- 2章 東京に行くぞ!
- 伊勢高校
- もやもや
- 東京大学オープンキャンパス
- 振るわない結果
- 地方学生の戦い方
- 変なメール
- 東京大学へ
- かもめのジョナサン
- 研究仲間
- 最終準備
- 全国大会 最終審査
- 表彰式
- 帰路
- 周りの反応
- 三重県知事表敬
- ALTの先生と日々
- 世界大会ISEF
- 抜け殻の日々
- 資金難
- お金と幸せ
- 推薦入試
- センター試験
- 合格発表
- 今、お金ないな
- 「一度は自分でやってみること」
- 東京へ!
- スタートライン
- 3章 祖父母のお金
- 東京大学三鷹国際学生宿舎
- 情報戦
- 奨学金がもらえない?
- 孫正義育英財団の面接
- カルチャーショック
- お金なら何とかならない
- 伊勢に逃げる
- 質問攻め
- 温かい居場所
- 成功と幸せ
- 孫さん
- 正財団生合格
- 父母のお金、祖父母のお金
- 東大で語られる「多様性」
- 学生の矜持
- 4章 働かせてください
- 「名刺アタック」とかばん持ち
- 成人式
- 僕はどう生きていきたいのか
- 古典に助けられる
- サイゼリヤ会長の講義
- ゲオホールディングス 遠藤社長
- 日本通信 福田社長
- 人生の先輩
- 憧れの大先輩
- 自分の戦い方
- 働くこと
- 新型コロナ
- 院試に落ちる
- 富岡製糸場のポール・ブリュナ
- 「働かせてください」
- 「君はあれから何をしてきた?」
- 「矢口太一の名刺アタック」
- 玉木代表
- 党首へのインタビュー
- 卒業式
- 次の舞台へ!
- 新社会人生活
- 科学的アプローチの推進
- 感謝と前進
- 想い
- あとがき
書籍紹介
矢口太一さんは1998年、三重県伊勢市生まれ。両親が高卒で、経済的に恵まれない環境の中、地方の公立高校に通いながら塾なしで東京大学工学部機械工学科に入学しました。大学時代は仕送りや貯金がなく、学費や生活費を自力で賄いながら卒業。その後、株式会社ゲオホールディングスで社長室秘書課特命担当として働き、現在は霞ヶ関キャピタル株式会社のAI Labでシニアストラテジストを務める傍ら、東京大学大学院新領域創成科学研究科の修士課程に在籍しています。
報われない現実と努力の仕方
彼は、「人生は生まれ落ちた瞬間にコースが分かれている」と述べ、努力だけでは報われない現実を指摘します。特に「普通の家庭」に生まれた人々がスタートラインに立つまでの苦労や工夫を、自身の半生を通じてリアルに描いています。東大入学や卒業、そして社会での挑戦といった過程で、彼がどのように困難を乗り越え、希望を見出してきたのかが伝わる一冊です。
興味があれば、この本を通じて矢口さんの視点や生き方に触れてみてはいかがでしょうか。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
「質×量」

「質×量」という表現で勉強や仕事のことが語られることがあります。しかし、同じ東大生と競うなか、同じ方向性で努力したら大差は生れないのではないかと考えるようになりました。努力を「どこに」向けるのかという戦い方もある気がしてなりません。
東大生が良い報酬を求めれば、弁護士、コンサル、商社、外資金融などの狭い領域しかないように見えました。私はこうした仕事をしたいわけではありません。会社四季報には上場企業がこんなにたくさんあるのに、活躍の場がここまで限られていることなどあり得るのでしょうか。
報酬や役割といった活躍の場を整えれば、意欲ある優秀な人材は世の中にもっと散らばっていくのではないかと、そんな道を切り拓くことはできないだろうかと考えるようになりました。
いつしか、自分が一番興味を持った会社の経営者に直接交渉して、活躍の場を得よう、そんな風に思うようになっていったのです。