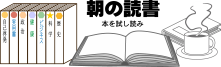※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
「保守思想」大全
名著に学ぶ本質
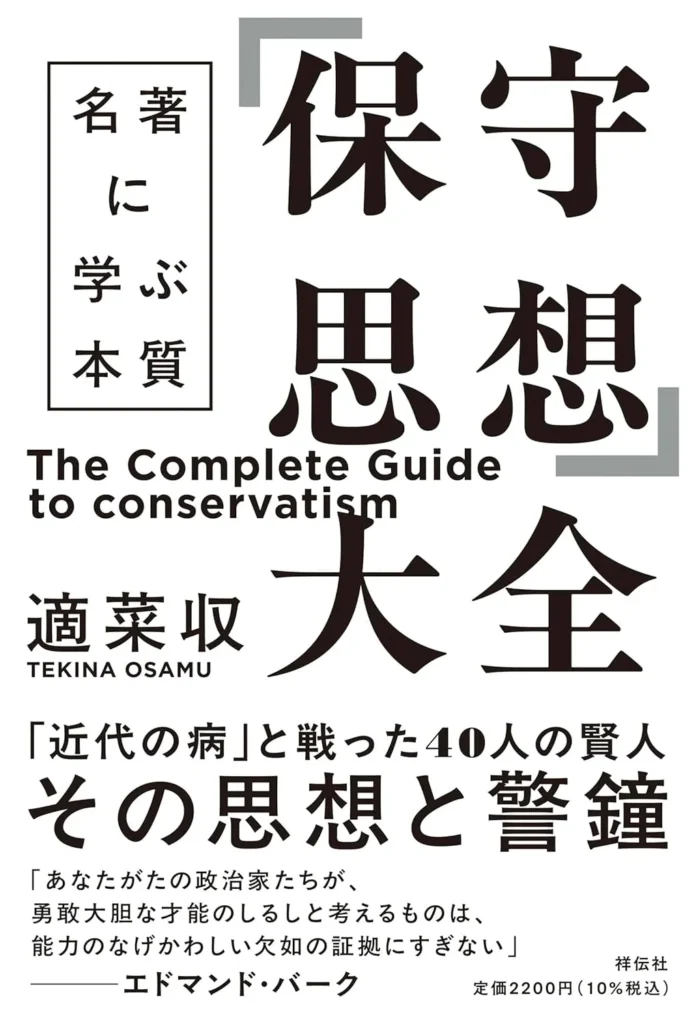
適菜収
作家。
ニーチェの代表作『アンチクリンスト』を現代語訳した『キリスト教は邪教です』や『安倍晋三の正体』など、著書50冊以上を執筆。
祥伝社
- はじめに「言い古されたこと」を繰り返す
- 第一章 保守主義とは何か
- 「保守的であるということ」 マイケル・オークショット
- 保守思想の核心
- 統治者の仕事とは
- 「フランス革命についての省察」 エドマンド・バーク
- 保守主義の父
- 「先入見」を重視
- 権力を与えてはならない人間
- 『保守主義的思考』 カール・マンハイム
- 保守主義と伝統主義
- 具体的なものへの執着
- 直線的な歴史観との戦い
- 「私の保守主義観」 福田恆存
- 保守主義を奉じるべきではない
- 合理主義は不合理
- 日本に保守が根づかない理由
- 『保守とはなにか』 江藤淳
- イデオロギーを警戒「主義」は必要ない
- ハイカラな明治憲法
- 『反啓蒙思想』 アイザイア・バーリン
- 反啓蒙思想=保守ではない
- デカルト主義の誤り
- 人間性の擁護
- 「保守的であるということ」 マイケル・オークショット
- 第二章 近代に対する警戒
- 『偶像の黄昏』 フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ
- 「反人間的なもの」に対する批判
- 近代の構造
- 概念の暴走
- 『ゲーテとの対話』ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
- フランス革命の本質
- 唯一神教的発想の傲慢さ
- 概念による世界の破壊
- 『暗黙知の次元』マイケル・ポランニー
- 言語化できない領域
- 科学主義への批判
- 伝統主義の重要性
- 『小林秀雄全集』 小林秀雄
- 意は二の次
- 文学の役割
- 漢ごころの根
- 「現代日本の開化」 夏目漱石
- 表層的な近代化
- 欺瞞の積み重ね
- 解決策も対案もない
- 「『さまよえる』日本人」山本七平
- 負の充足
- 啓蒙主義の絶対化
- 超国家主義から超戦後主義へ
- 『近代性の構造』 今村仁司
- 体系主義と方法主義
- 意志の時代
- 排除と差別のプログラム
- 『偶像の黄昏』 フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ
- 第三章 熱狂する大衆
- 『大衆の反逆』ホセ・オルテガ・イ・ガセット
- 大衆とは何か
- 超デモクラシーの勝利
- 無恥と忘恩
- 『群衆心理』ギュスターヴ・ル・ボン
- 野蛮人と化すメカニズム
- 統率者を求める
- 『世論と群集』ガブリエル・タルド
- 公衆と群集
- メディアが世論を生み出す
- 借り物の思考に追随
- 『世論』 ウォルター・リップマン
- 見たいものしか見ない
- 簡単な説明には要注意
- マルクス主義の誤り
- 『現代の批判』セーレン・キルケゴール
- 情熱のない時代/隣人が判断基準
- 『知識人の生態』西部邁
- 大衆の価値観と距離を置く人
- 絶望を感受する
- 『知識人とは何か』エドワード・W・サイード
- 知識人とは何か
- コメンテーターの対極
- 「リマインダー」の役割
- 『エピクロス 教説と手紙』 エピクロス
- 臆見を追い払う
- 苦しみを取り除く
- ニーチェへの影響
- 『大衆の反逆』ホセ・オルテガ・イ・ガセット
- 第四章 全体主義との戦い
- 『法の精神』 シャルル=ルイ・ド・モンテスキュー
- 権力への警戒
- 政体は腐敗する権力の集中は地獄を生む
- 『アメリカのデモクラシー』 アレクシ・ド・トクヴィル 函
- 新しい形の隷属
- 強烈な自治の伝統
- 『大衆運動』エリック・ホッファー
- 大衆運動の共通点
- 服従したいという熱意
- 『自由からの逃走』エーリッヒ・フロム
- 自由の拒絶
- ナチズムのための心理的な準備
- 指導者への隷属
- 『フランクフルト学派』 細見和之
- ホルクハイマーの思想
- 伝統的理論と批判的理論
- 啓蒙に内在する問題
- 『マクドナルド化する社会』ジョージ・リッツア
- ウェーバーの合理化理論
- 脱人間化の原理
- 『一九八四年』ジョージ・オーウェル
- 歴史の改竄
- 「事実」は意味を持たない言葉の破壊
- 「身からでたさび」 ハンナ・アレント
- 聴衆が要求するもの
- 宣伝とマーケティング
- 過去は過ぎ去っていない
- 「真の個人主義と偽の個人主義」フリードリヒ・A・ハイエク
- 政治用語の混乱
- 緩衝材としての中間団体
- 少数者の権利を擁護
- 『法の精神』 シャルル=ルイ・ド・モンテスキュー
- 第五章 誤解されたナショナリズム
- 『民族とナショナリズム』 アーネスト・ゲルナー
- 近代国家の原理
- 国家による強制
- 匿名的で非人格的な社会
- 『定本想像の共同体』 ベネディクト・アンダーソン
- 特殊な文化的人造物
- なぜ「想像」なのか
- 出版資本主義
- 『ナショナリズムとは何か』 アントニー・D・スミス
- ナショナリズムの四分類
- 宗教に近い機能
- 西欧中心主義
- 『決定版三島由紀夫全集』 三島由紀夫
- 右翼とは対極
- 「言葉」を守る
- ご都合主義の愛国
- 『ホモ・ルーデンス』 ヨハン・ホイジンガ
- 「遊び」とは何か
- 小児病的挙動
- 『民族とナショナリズム』 アーネスト・ゲルナー
- 第六章 歴史と古典
- 『歴史とは何か』E・H・カー
- 「事実はみずから語る」は嘘
- 歴史家は中立的ではない
- 現在と過去との対話
- 『哲学入門』 カール・ヤスパース
- 人間を規定する「状況」
- 歴史の意義
- 答えよりも問いが重要
- 「日本の創意」 折口信夫
- 『源氏物語』という奇跡
- 反省の文学
- 作為を超えたもの
- 『古文の読解』 小西甚一
- 古文を読みこなすためのヒント
- 「もののあはれ」とは何か
- 古典を読むことは歴史を学ぶこと
- 『日本人の美意識』 ドナルド・キーン
- 日本の美しさ禅の美学
- 振り返るべき日本の歴史
- 『歴史とは何か』E・H・カー
- おわりに 古人の言葉に含まれているもの
書籍紹介
この本は、保守思想について深く掘り下げる内容となっており、その歴史や哲学、主な思想家たちの視点を通じて、現代における保守主義の意義を紐解いています。適菜収さんは、複雑なテーマをわかりやすく解説する手腕で知られており、この作品でもその力が存分に発揮されています。
保守という意味
単に政治的な立場を述べるだけでなく、文化や伝統、価値観といった広い視野から保守思想を捉えているのが特徴です。読者は、保守という言葉が持つ多様な意味や、それが社会の中でどのように機能してきたかを学ぶことができます。特に、日本の文脈における保守思想の独自性にも触れられており、グローバルな視点とローカルな視点がバランスよく織り交ぜられています。
保守思想の入門書
保守思想に興味があるけれどどこから手を付けたらいいかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。そんな方にとって、「保守思想」大全は最適な入門書と言えるでしょう。
保守思想に初めて触れる方でも抵抗なく読み進められるよう、丁寧な構成が意識されていると感じます。思想書としてはハードルが高いイメージがありますが、筆致は親しみやすく、専門知識がなくても楽しめる一冊に仕上がっています。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
「現代日本の開花」 夏目漱石

近代の保守思想を理解するという意味で、明治44年に行われた夏目漱石の講演「現代日本の開花」を学ぶと、近代の問題の本質が見えてくるのではないでしょうか。
日本は開国しなければならない状況に追いつめられ、西洋のモデルをお手本に近代社会を改造しました。近代の受容が表層的なものであるのは当然です。日本の近代化におけるものが内発的なものであったというのは欺瞞で、文明が自ら開化したという内容も表面的なものであったと、夏目漱石は嘆いています。
人間活力の発展の経路たる開花というものの動くラインもまた波動を描いて弧線を幾つも幾つもつなぎ合わせて進んでいくといわなければなりません。むろん描かれる波の数は無限無数で、その一波一波の長短も高低も千差万別でありますが、やはり甲の波が乙の波を呼び出し、乙の波が丙の波波を誘い出して順次に推移しなければならない。一言にしていえば開花の推移はどうしても内発的でなければ嘘だと申し上げたいのであります。
我が国の「保守派」の軽薄さ、幼稚さに対しても夏目漱石は警告しています。
とにかく私が解剖したことが本当の所だとすれば我々は日本の将来というものについてどうして悲観したくなるのであります。外国人に対して乃公(自分)の国には富士山があるというような馬鹿は今日は余りいわないようだが、戦争以後一等国になったんだという高慢な声は随所に聞くようである。中々気楽な見方をすればできるものだと思います。
このご時世、正気を維持していれば、神経衰弱にもなりかねません。しかし、少しづつ向き合うのがよろしいのではと言っておきます。そう、漱石は締めくくりました。
ではどうしてこの急場を切り抜けるかと質問されても、前申した通り私は名案も何もない。ただできるだけ神経衰弱に罹らない程度において、内発的に変化して行くのが好かろうというような体裁の好いことを言うより外に仕方がない。