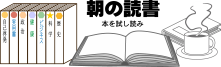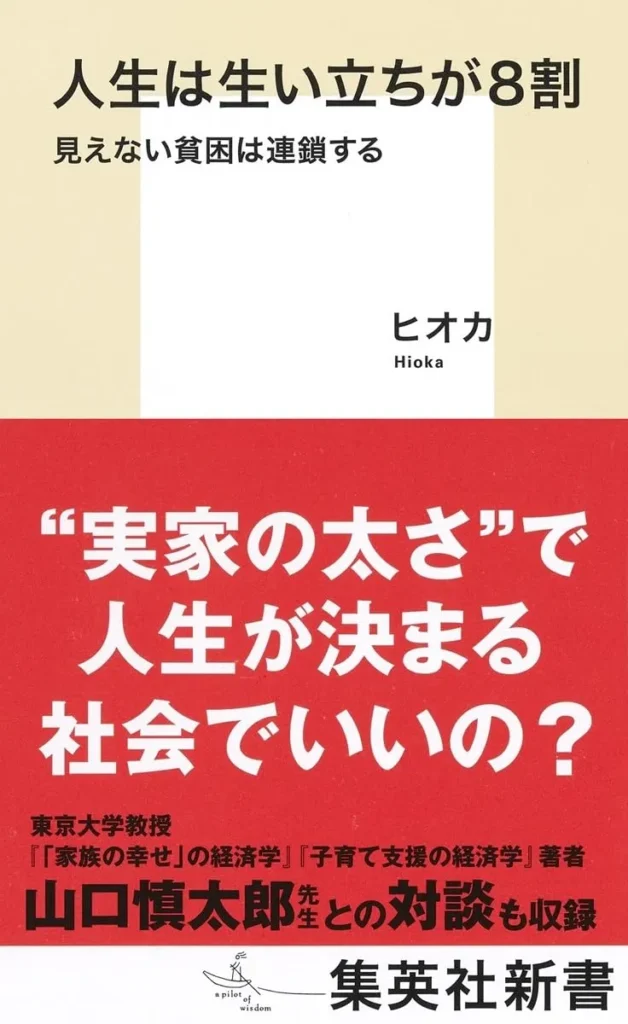※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
人生は生い立ちが8割 見えない貧困は連鎖する
ヒオカ
ライター。
社会問題からエンタメまで様々なデーまで取材・執筆。
集英社
- まえがき
- 第一部 見えない貧困は連鎖する
- 「健康的で文化的な最低限度の生活」
- 貧困は精神的余裕を奪う
- 「ズルい」「贅沢だ」で切り捨てられるもの
- 大人の貧困は同情されない
- 貧困問題は人権問題である
- 教育格差の実態
- 奨学金をめぐる議論
- キッズドア・玉木絵梨さんインタビュー
- 地域若者サポートステーション・寺戸慎也さんインタビュー
- 「弱者」が優遇されている?
- 「まとも」「普通」に生きられなかった人への想像力を
- 「選ばない」と「選べない」は違う
- 見えない格差 ①文化資本
- 見えない格差 ②非認知能力
- 見えない格差 ③貧困税
- スタートラインは平等ではない。一人ひとり違う
- 「標準モデル」のレベルが高すぎる
- 第二部 ヒオカ×山口慎太郎 学問の最先端から見えてくる、現実を変える方法
- 「非認知能力」の格差とは
- 「非認知能力」は後天的に身につけられるか
- 保育所利用の問題点
- 学歴が高いと、しつけの質も高くなる理由
- 「非認知能力」を形成するには
- 「文化資本」の何が子どもに影響するか
- 情報格差がもたらす申請主義の問題点
- 親子で似やすい行動とは
- 健康行動も文化資本で決まる
- 親子で職業が似てくる理由
- 胎児のときの影響が大人になっても…?
- 不摂生は「自由意志」か?
- 「諦め」は生育環境から
- リスキリングを必要とする人こそ、リスキリングに向かえない
- 「他人を信頼する」社会関係資本が困難だと……
- 「体験格差」は贅沢か?
- 奨学金は「出世払い」にせよ
- 所得の再分配は経済成長に直結する
- 「税金」に対する大いなる勘違い
- 貧困対策は社会への投資
- 稼ぐ能力はどこからくる?
- 少子化は「人権問題」である
- データを見れば「自己責任論」は言えなくなる
- なぜ日本は「自己責任論が強いのか
- 格差は本当に広がっているのか?
- 今こそ投資と再分配を
- これからの社会に必要なこと ①同一労働・同一賃金の徹底を
- これからの社会に必要なこと ②教育機会の均等を
- 「Fラン」大学批判が見落としているもの
- 奨学金制度の盲点
- 結局は親子であらゆるものが似る
- あとがきにかえて
- 親の貧困、子に報い?
- 分断を溶かすために
- 人生の結果は生い立ちか努力か
書籍紹介
著者のヒオカさんは、自身が貧困家庭で育った経験を持つライターで、そのリアルな視点から貧困がどのように人生に影響を与え、次の世代へと連鎖していくのかを綴っています。
著者の格差体験
貧困と一口に言っても、目に見える困窮だけではなく、習い事や修学旅行に行けないといった「体験格差」や、自己肯定感や忍耐力といった「非認知能力」が育ちにくい環境がもたらす「見えない貧困」にも光を当てています。こうした見えない部分が、実は人生の大きな部分を占めているという主張が、読む者の心に響きます。
貧困から抜け出すのは困難
努力だけではどうにもならない現実や、生まれ育った環境が個人の選択肢をどれだけ狭めてしまうのかが、具体的なエピソードとともに語られています。さらに、東京大学大学院の山口慎太郎教授との対談も収録されており、学術的な視点から「親から子へと受け継がれるもの」を考察しているのも興味深いです。貧困を断ち切るための政策や方法についても提案がなされていて、社会全体で考えるべき課題として読者に投げかけています。
貧困の人に寄り添う文章
感情的でありながらも冷静で、貧困という重いテーマを扱いつつも読者を突き放すことなく寄り添うような温かさがあります。1995年生まれの彼女は、社会問題からエンタメまで幅広いテーマで執筆しており、これまでに『死にそうだけど生きてます』や『死ねない理由』といった著書も出しています。この本でも、彼女らしい「弱者の声を可視化する」という姿勢が貫かれていて、貧困を他人事ではなく自分事として感じられるよう工夫されています。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
情報格差がもたらす問題点

貧困層ほど情報弱者である場合があります。富裕層、一般家庭といった余裕のある層が、無料で体験できる講座の情報収集が上手なので、無利子の奨学金とか制度の情報を掴むことができます。
普段の仕事量が多く、時間や精神に余裕がないこともあります。低所得者だと、そもそもの認知能力の限界があり、計画的に物事を進めることができないので、能力に限界があり、情報を見つけるに至らないことが多いようです。
書類を読み解く力はまさに学力です。学力がないと、手続きができなくて、必要な支援を受けることができません。申請のハードルをどれだけ下げるのかというのが、本来の目的達成のためには必要だと思います。
奨学金の申請書をソフトウェアが全て記入し、あとはサインするだけというところまで自動化してあげるようなプッシュ型支援してあげると、大学進学率があがるという結果はアメリカで実証されています。
今こそ投資と再分配を

社会が不安定では、投資はあまり行われません。民間企業の投資も行われにくくなります。
社会保険料が高すぎて、年収200万円でもしっかりした額を持っていかれます。低所得者は減らず、結果的に不健康な人や犯罪が増えているようです。社会全体のコストを抑える意味でも、再分配は必要です。
日本の税だと、高所得者ほど控除を受けやすいという特徴があります。低所得者だと、控除の恩恵が受けにくいのです。控除が市民にとって切迫したものなのは、フリーランスになってから痛感いたします。
児童手当などの給付も、どっからか潰しの声がかかります。自分がもらえないもの、自分がとられるものは全部潰してしまいたいと思ってしまうものでしょう。年金や医療、マイナンバーは総体としてあったほうがいい社会保障でも、政治に信用がないと疑いが向けられてしまうようです。生活保護受給者とか特定の低所得者への支援が拡充されると、自分が損をする感覚になってしまいます。誰に対しても利益はある制度のはずでもです。
消費税と別の給付をセットにする国があります。カナダだと年度末に所得確定申告すると、それに応じて還付金が発生します。低所得世帯に小切手が届くような形でバランスをとっています。日本でも同じようにバランスをとれると思います。この税金と再分配の話は、今後も何周もするでしょう。