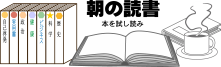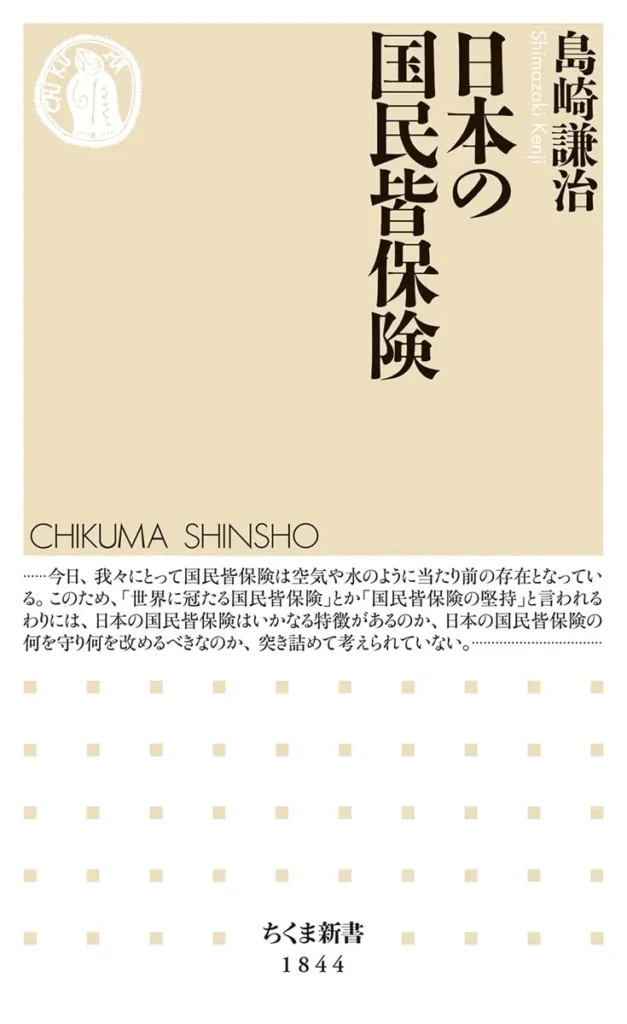※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
日本の国民皆保険
島崎謙治
筑摩書房
- プロローグ
- 1部 構造
- 第1章 日本の医療制度の特徴と概要
- 医療制度の特質と国民皆保険の射程
- 医療制度の国際比較
- 日本の医療財政制度の概要
- 日本の医療提供制度の概要
- 第2章 日本の国民皆保険の要諦
- 職域保険(被用者保険)と地域保健(国民健康保険)の二本建て
- デリバリー(医療提供)とファイナンス(医療財政)との結合
- 第3章 制度設計をめぐる論点と分析方法
- 国民皆保険の制度設計をめぐる重要論点
- 分析方法 経路依存性
- 第1章 日本の医療制度の特徴と概要
- 2部 軌跡
- 第4章 基盤形成期
- 健保法の制定と発展
- 国民健康保険法の制定と普及
- 医療の実施組織と診療報酬の支払方法
- 第5章 確立・拡充期
- 医療保険制度の再建
- 国民皆保険の構想と実現
- 国民皆保険後の保険給付および医療提供体制の拡充
- 第6章 見直し・改革期
- 老人保健制度および退職者医療制度の創設
- 医療提供制度の改革と海保保険制度の創設
- バブル経済の崩壊と医療保険制度改革
- 社会保障・税一体改革および全世代型社会保障改革
- 第7章 軌跡をめぐる論点と考察
- 軌跡をめぐる論点
- 社会保険方式の意義と受容
- 被用者保険と国民健康保険の2本建ての国民皆保険
- 高齢者医療制度の制度設計
- 第4章 基盤形成期
- 3部 展望
- 第8章 社会経済の変容と制約条件
- 社会経済と国民皆保険の関係
- 将来の人口構造の変容
- 2040年頃の社会保障の将来見通しと視点
- 第9章 医療提供制度をめぐる課題と改革
- 医療政策の理念
- 医療機関の機能分化と連携
- 医師の働き方改革
- 医療従事者の確保と遍在是正
- 地域医療構想の推進
- 地域特性に応じた取り組み・実践事例
- 物価・賃金の上昇と診療報酬の対応
- 第10章 医療保険制度をめぐる課題と改革
- 被用者保険と国民健康保険の2本建ての体系の是非
- 働き方の多様化と被用者保険の適用拡大
- 被用者保険における被扶養者をめぐる政策課題
- 国民健康保険制度
- 高齢者医療制度
- 医療保険の財源論
- 混合診療解禁論の是非
- 第8章 社会経済の変容と制約条件
- エピローグ
- あとがき
書籍紹介
日本の国民皆保険制度がどのように生まれ、発展してきたのか、その歴史と構造を丁寧に紐解いています。国民皆保険とは、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、必要な時に医療を受けられる仕組みのことです。日本では1961年にこの制度が実現し、今では私たちにとって当たり前の存在となっています。本書を読むと、国民皆保険の裏には先人たちの知恵と努力があったことが、よくわかります。
これからの健康保険制度のあり方
少子高齢化や生産年齢人口の減少、2040年問題、物価や賃金の上昇、医師の偏在といった現代の課題に目を向けながら、国民皆保険の未来についても考えさせられる内容になっています。例えば、高齢者が増える一方で働き手が減る中で、どうやってこの制度を持続させていくのか。あるいは、地域ごとの医療格差をどう解消していくのか。そうした問いに対して、過去の経緯を踏まえつつ具体的な展望を示してくれるのです。
いろんな角度の知識からわかりやすく解説
文章はとても読みやすく、専門的な知識がなくても理解できるように書かれています。日本の医療制度が海外と比べてどのような特徴を持っているのかなど、国際比較を通じて明らかにする部分は新鮮な気づきを与えてくれるでしょう。
国民皆保険が単なる制度ではなく、社会全体で支え合う精神の結晶だということです。しかし、経済や人口構造の変化によって、その形が崩れてしまうリスクもあると警告しています。だからこそ、私たち一人ひとりがこの制度の価値を再認識し、未来のために何ができるかを考えるきっかけになるはずです。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
高齢化の進展

老年人口は2040年頃まで増加します。「団塊ジュニア世代」が65歳以上になるのが、2040年頃だからです。その後、老年人口は減少に転じます。
これは医療・介護の需要を考えるうえで非常に重要な点です。1963年は100歳以上の人口が153人だったものが、2024年には9.5万人に増えました。そして、2051年には46.9万人に達すると算出されています。
筆者は、社会保険料を単なる負担と考える字風潮や社会保障を経済成長の足かせのように捉えることに違和感を覚えています。社会保障は国民の安心安全を支えることに寄与もしているはずです。健康を守るための医療費の効率的な使用にも貢献しています。社会保険の役割を批判するのではなく、正当に評価しなければ、国民の反感や反発を招き、必要な社会改革が進まないでしょう。
今、国民の約半数が社会保障の給料水準を維持・向上するために負担増はやむを得ないと思っています。負担が重いと感じているわけです。各種所要財政の整頓をして、政策を吟味し、国民がその政策と税収の必要性に理解を得ることが求められています。
75歳以上が急増するにあたって

医療・介護の保険を維持するならば、輸出関税の中立をして、所得税や間接税でも安定して税収ができる消費税の引き上げをすれば簡単に財源が確保できます。政府が借金をして国際を刷りすぎることで起きる副作用を抑えようとすれば、国境税の調整という観点からも特に消費税の増税が引き上げられるのではないでしょうか。
とはいえ、社会保障のためとはいえ国際競争力に影響を与えてまで税目の吊り上げをするのは適当ではなく、医療費の自己負担率の割合を引き上げることも勇気がいるといった状態になっています。
(※著者の意見です。)