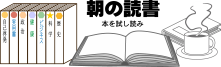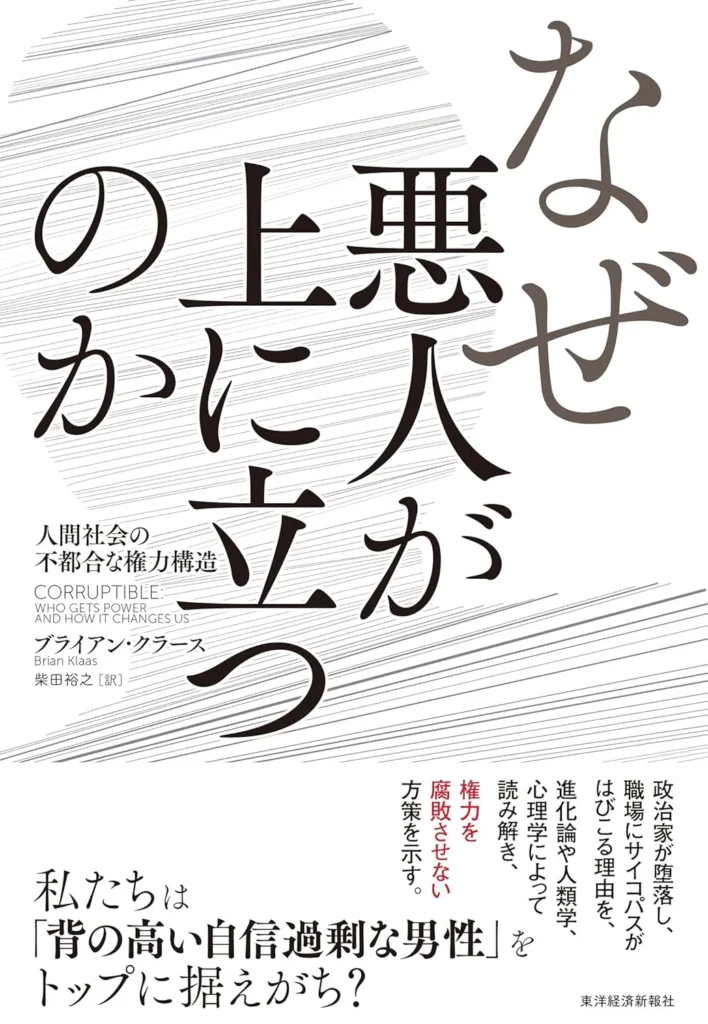※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
なぜ悪人が上に立つのか
ブライアン・クラース
ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの国際政治学の准教授。
『アトランティック』誌の寄稿者で、『ワシントン・ポスト』紙の元ウィークリー・コラムニスト。
東洋経済新報社
- 第1章 序権力はなぜ腐敗するのか?
- ピーコン島の悲劇
- 無人島で協力し合って生き延びた少年たち
- 権力に関する4つの疑問
- マダガスカルの独裁者
- スタンフォード監獄実験が明らかにしたこと
- 私たちは顔だけで指導者を選んでいる?
- 劣悪な制度が腐敗した権力者を生むのか?
- 権力に関する4つの仮説
- 第2章 権力の進化史
- チンパンジーの権力闘争
- ヒトとチンパンジーを隔てるもの
- 3歳児は不正を嫌う
- 平等な社会を築くためのクン族のしきたり
- 「肩」が変えた私たちの社会構造
- 人間の集団は平等主義だった 有史以前の社会の「厄介者」
- 個体だけでなく集団の質も生き残りを左右する
- 戦争と遠距離武器の拡がり
- 農業革命と複雑な社会の誕生
- フォー・アンド・ビーズ
- 「戦争と豆」がもたらした階級社会への移行
- 第3章 権力に引き寄せられる人たち
- 「目に見えない飛行機」を見た統計学者
- 「生存者バイアス」の3つのレベル
- 「人食い皇帝」の支配欲は生まれつきだったのか?
- 「リーダーシップ遺伝子」は存在するのか?
- 攻撃的な人を引きつけてしまう警察署の採用活動
- 警察官にふさわしい人物の応募を増やしたニュージーランド警察の試み
- ホームオーナーズ・アソシエーション
- 権力に引きつけられた住宅所有者管理組合の独裁者
- 第4章 権力を与えられがちな人たち
- 中国で重宝される偽の白人ビジネスマン
- リーダーは白人男性だらけ
- 権力の「シグナリング」
- 地位や権力を伝える方法
- 石器時代の祖先による指導者選び
- 石器時代の脳は強そうな男性をリーダーに選びがち
- 背の高さへの偏好という進化のミスマッチ
- 人種差別の起源と「内集団」と「外集団」への選別
- 権力を得るうえで童顔は有利か不利か?
- 差別や偏見を克服するための4つの措置
- 第5章 なぜサイコパスが権力を握るのか?
- マフィアのボスのように振る舞った学校のメンテナンス職員
- 「ダークトライアド」の特徴
- サイコパスとはどのような人たちか?
- 役員室にいる「スーツを着たヘビ」のようなサイコパス
- サイコパスは冷徹で計算高い
- 自信過剰な人が出世する理由
- 第6章 悪いのは制度か、それとも人か?
- 主食が米か麦かで行動や考え方が異なる?
- 私たちが陥りがちな「根本的な帰属の誤り」
- 悪質な行動は人のせいか制度のせいか?
- 巣の構造がハチを利己的にする?
- 「建築王」にして「虐殺王」だったレオポルド2世
- 独裁政権を民主政権へと移行させる任務を担った男
- 劣悪な制度の下での真っ当な人物による選択
- 第7章 権力が腐敗するように見える理由
- 権力は本当に腐敗するのか?
- 大量殺人の罪に問われた元首相
- 権力者は手を汚さなければならない状況に立たされる
- 学習によって盗みがうまくなっただけ?
- 独裁者は不正を働くことに上達する
- 奇妙な個人崇拝は忠誠審査という戦略的で合理的な役割を果たす
- 権限のある地位に就けば悪行を働く機会が自ずと増える
- 極限状態でのトリアージの末の安楽死は殺人か?
- 権力者は活動を監視されているので悪行が露呈しやすい
- 第8章 権力は現に腐敗する
- バイオテロリストになった芸術家志望の学生
- 権力のある人は自分を抑制する力を失う傾向にある
- 対象とするサンプルが偏っているという問題
- 権力が人を腐敗させることを示した実験
- 調査結果は完璧なものとは言えない
- 第9章 権力や地位は健康や寿命に影響を与える
- 下位のサルは薬物を好む?
- 地位と裁量権とストレスの関係
- ストレスが少ないのはアルファオスよりベータオス
- ストレスの強い環境下にあるCEOは寿命が短くなり加齢が進む
- 階級の「中の上」あたりがちょうど良い
- 社会的関係が免疫機能を高める
- 第10章 腐敗しない人を権力者にする
- レッスン1 腐敗しない人を積極的に勧誘し、腐敗しやすい人を篩い落とす
- レッスン2 籤引き制と影の統治を利用して監督する
- レッスン3 人事異動をして権力の濫用を減らす
- レッスン4 結果だけではなく、意思決定のプロセスも監査する
- 第11章 権力に伴う責任の重みを自覚させる
- レッスン5 責任を頻繁にしっかりと思い出させる仕組みを作る
- レッスン6 権力を握っている人に、人々を抽象的なもののように考えさせない
- 「心理的距離」の4つの尺度
- 心理的距離による人間性の剥奪
- 心理的距離が増加した現代社会
- 第12章 権力者に監視の目を意識させる
- レッスン7 人は監視されていると善良になる
- レッスン8 支配される側ではなく支配する側に焦点を合わせて監視する
- レッスン9 ランダム性を利用して抑止力を最大化しつつ、プライバシーの侵害を最小化する
- 第13章 模範的な指導者を権力の座に就けるために
- レッスン10 高潔な救済者の出現を待つのをやめる。代わりに、彼らを生み出す
書籍紹介
この本では、権力やリーダーシップの裏側に潜む人間の本質について深く掘り下げています。クラースは、心理学や社会科学の視点から、なぜ時に「悪人」と呼ばれるような人物が組織や社会の頂点に立つのかを丁寧に解説しています。彼の分析は、単なる批判にとどまらず、そうした現象が起こる背景や仕組みに光を当てている点で魅力的です
道徳が薄れる
権力が人の行動や価値観にどのように影響を与えるかというテーマです。クラースは、具体的な事例や研究を交えながら、権力を持つことで道徳観が歪んでしまうケースがあることを示しています。また、社会がそうした人物をリーダーとして選んでしまう理由についても考察しており、読者に自分たちの選択や判断について考えさせるきっかけを与えてくれます。
権力者を学ぶ
単に「悪」を糾弾するものではなく、私たち全員が持つ可能性や傾向について問いかける内容となっています。読み進めていくうちに、リーダーシップとは何か、正義とは何かを改めて見つめ直したくなるでしょう。ビジネスマンや社会問題に関心のある方にとって、実践的な気づきを得られる一冊と言えます。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
サイコパスとはどのような人たちか?

サイコパスは、アリグモと共通点が多い。彼らはクモの卵は食べないし、両腕を触角のように宙に差し上げながら、絹糸でできたアパートで暮らしているわけでもありません。自分とはまったく違うもの、正常に機能している脳を持つ人々を、しばしば真似します。真似をしながら、そういう人々を餌食にすることが多いのです。
神経科学者はまだ共感を理解しようと努力している段階にありますが、共感は「ボトムアップ」と「トップダウン」の2つのシステムを通して動くようにできているようです。
トップダウンのシステムは、「メンタライジング」と呼ばれるものに由来します。他者が感じていることや、他人がどんな意図を持っているかを理解するものです。
ボトムアップのシステムは「ミラーニューロン・システム」と結びついていると考えられています。何かひどい臭いを嗅いだかのように誰かが顔をしかめると、あなたもひどい臭いを嗅いだかのように脳の一部が活性化するシステムです。幸せそうな人みると幸せに感じたり、悲しそうな人を見ると悲しくなったりする「情動感染」という現象に関係があるのではと研究されています。
ところが、誰もが同じわけではなく、他人の苦しみに対しての反応が大きい人も小さい人もいるのです。サイコパスと臨床診断された人に、人が別の人に痛めつけられている動画を観させてもニューロンの発火がまったく起こりません。通常は情動と関連している脳の部位が、サイコパスは反応しないのです。
権力が人を腐敗させるか

「独裁者ゲーム」という実験で、権力が人を悪質にするかどうかを調査した結果がいくつもあります。参加者の1人をランダムに選び、独裁者に指名し、誰がどのくらいもらうかを決める権力を与えるといったのです。お金はすべて本物を使い、条件を変えて、人々が利己的に振る舞うか、無欲で振る舞うかを観察します。
「低権力」条件では、独裁者が不公平に扱う確立は39%でした。「中権力」条件では、不公平に扱う確立が61%に跳ね上がります。「高権力」条件では78%の不公平を確認できたようです。また、テストステロン値が人ほど、リスクを冒してまで不公平なほどまでに分配する傾向もあります。
権力を持った人の行動は、他者の話を遮ったり、人や物事を型にはめたり、意思決定をするときにあまり道徳的ではない論法をつかったり、自分が見せる行動を他者が示すと批判的になることが増えます。権力を持つと否定的な影響を受けるといった証拠は曖昧なものになってしまうけれど、権力をもつことで道徳的になることを示す調査はほとんどありません。