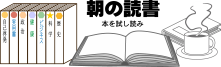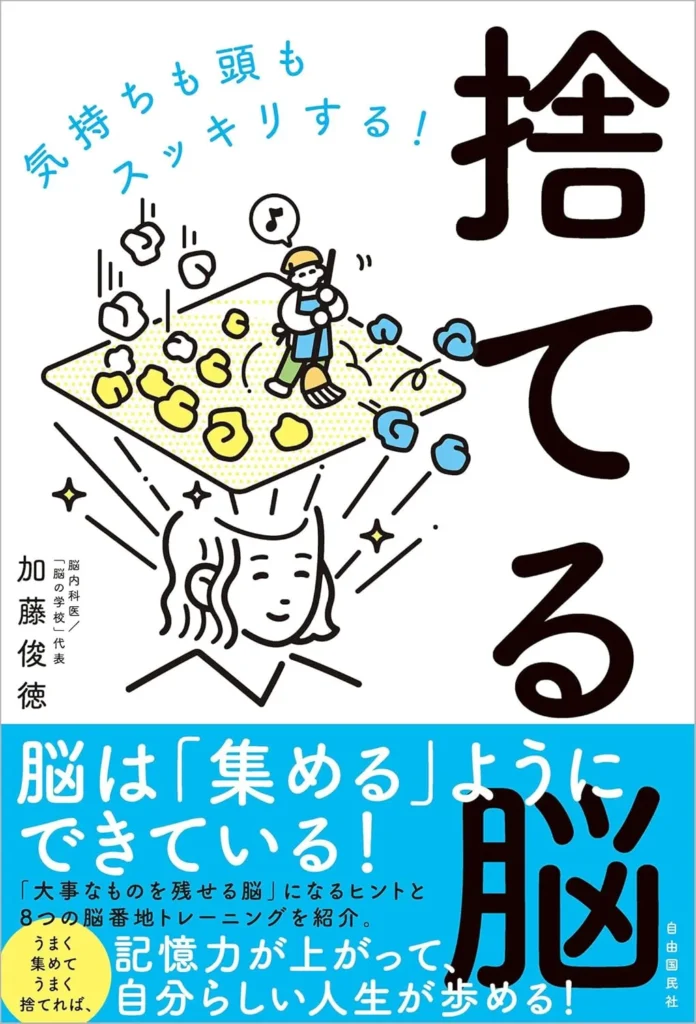※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
気持ちも頭もスッキリする!
捨てる脳
加藤俊徳
脳内科医、医学博士。
加藤プラチナクリニック院長。
株式会社「脳の学校」代表。
昭和大学客員教授。
脳科学・MRI脳画像診断・ADHDの専門家。
米ミネソタ大学にてMRI脳画像研究に従事し、発達障害と関係する「海馬回旋遅滞症」を発見。
自由国民社
- はじめに
- 第1章 捨てられないのは脳のせいだった!
- 人の脳はもともと「集める脳」になっている!
- 「うまく集める脳」にならないと脳は劣化する!
- 「捨てる脳」の最重要脳番地は記憶系
- 「快・不快」の感情系にも左右される?
- 「捨てる脳」の5つのメリット
- Column① 捨てられない男、捨てられる女
- 第2章 「捨てる脳(=大事なものを残せる脳)」に変わる秘訣
- 「捨てたいモノ」には記憶別に3つのランクがある
- 「捨てる脳」の「3つの心得」
- 脳番地を動かして「捨てる脳」になる「8つの習慣」
- 第3章 「捨てられない脳」を記憶別に改善する脳番地トレーニング
- 直近記憶「運動系を動かして今すぐ捨てる」
- 事例(1)レシートなどどうでもいいモノがずっとカバンに入っている
- 事例(2)そもそも「捨てる」行動がおっくう
- 事例(3)片づけ本を読んでばかりで、実際は片づけられない
- 事例(4)DMやお知らせメールが溜まりがち
- 事例(5)ゴミ入れ用ビニール袋が溜まりすぎて、それ自体がゴミ化
- 事例(6)自分では散らかっている自覚はないが、家族は呆れている
- 事例(7)家族から「捨てて」と言われても「捨てられない」
- Column② 散らかっている家はストレスが高い?
- ワーキングメモリ「期限を決めて考えてから判断する」
- 事例(1)リサイクルショップに持っていこうと思って溜め続けている
- 事例(2)目の前にあふれるモノを見ていると片づける気にならない
- 事例(3)ボロくなった靴下を、まだはけるからいいかと放置
- 事例(4)古くていらない本もあるかもしれないけど、分類が面倒
- 事例(5)納豆の辛子、お刺身の山葵や醬油がどんどん溜まる
- 事例(6)筆立てに書きづらくなったペンが複数あるが放置
- 事例(7)困ってないから、わざわざ捨てなくてもいい気がする
- 事例(8)「要」「不要」「保留」で分けたが、「保留」が多すぎ
- 事例(9)旅行先の地図やパンフを捨てないで持っている
- 事例(10)子どもの園や学校などの書類がどんどん溜まっている
- 長期記憶「過去を回想しながらじっくり考える」
- 事例(1)子どもの工作や本をなかなか捨てられない
- 事例(2)40年以上前に買ったマッサージチェアを捨てられない
- 事例(3)体形が変わって着られない服をとってある
- 事例(4)捨てたら思い出がなくなると感じて写真などを溜め込んでいる
- Column③ 「選べない」「決められない」場合のヒント
- 直近記憶「運動系を動かして今すぐ捨てる」
- 第4章 家族が捨ててくれない場合の診断と対策
- 家族の事例(1)子どもがいらないモノを、隣の部屋や親の部屋に勝手に置く
- 家族の事例(2)「こうして捨てて」と言っても、言われたとおりに捨ててくれない
- 家族の事例(3)家族がゴミ・リサイクル回収の分別を理解していなくてイライラ
- 家族の事例(4)義父はリビングの散らかりにはうるさいが、自室はうん10年そのまま
- 家族の事例(5)夫に捨てる話をすると「すぐまた捨てるって言う!」とキレられ、捨てられない
- 家族の事例(6)夫が自室に趣味のモノを溜め込んでいる。使わないモノはどうにかしたい
- 家族の事例(7)実家の片づけに悩んでいる。「捨てたい父」と「捨てたくない母」のせめぎあい
- おわりに
書籍紹介
この本は、私たちが日々感じる「捨てられない」心理とその解決策を脳科学の視点から説明しています。加藤氏は、脳内科医であり、MRI脳画像診断やADHDの専門家として知られ、その経験を活かして「捨てる脳」という概念を提唱しています。
物を捨てられない
物を捨てることがなぜ難しいのか、それが脳のどの部分とどう関連しているのかを明確に示しています。読者が自分の脳を理解し、無駄なものを捨てることで精神的なスッキリ感を得る方法を具体的に教えてくれます。さらに、長期記憶と捨てる行為の関係性についても触れられており、記憶の整理がいかに重要かを理解させてくれます。
ストレス改善につながる
単に片付けのノウハウにとどまらず、脳の機能改善を通じて生活そのものをより快適にする方法を示しています。読者はこの本を通じて、自分がなぜ特定の物に執着するのか、そしてその執着をどうすれば解放できるのかを学ぶことができます。それは、物質的な整理だけでなく、心の整理にもつながるため、日常生活におけるストレスの軽減や、集中力の向上、さらには自己理解の深化にも大いに役立つでしょう。
捨てよう
片付けに悩む人だけでなく、自己啓発や脳科学に興味がある人にとっても価値ある一冊です。加藤俊徳氏の専門知識と実践的なアドバイスが融合した「捨てる脳」は、読者が自分自身の脳を再発見し、より健康的で生産的な生活を送るための手引書と言えます。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
ワーキングメモリにはキャパがある

ワーキングメモリは、人の意識に大きく支配されます。眠気のある状態では、うまく思考できません。個人差だけでなく、脳の覚醒状態(意識レベル)によって変わってくるのです。
ワーキングメモリによる短期記憶というのは、あることだけをインプットするのではなく、これまでに得た知識、感情、状態と連動しているので、嫌な気持ちになるような記憶が占める割合が多いと、気分よく日々を過ごせません。
仕事が8割、残りの2割が悩みごとでワーキングメモリの容量を占めていればまだ良い方ですが、悩みが増えて仕事に使うワーキングメモリを4割しか使えないとなると、仕事や家事、社会活動など、やるべきことができなくなるでしょう。
日ごろから、ワーキングメモリに影響を与えない程度に悩みを捨てておく必要があります。悩みを捨てて、やりたいこと、やってみたいことなど、前向きになれるものを脳に集めておくのが理想です。
3つの基準

枠を決める
捨てる基準、残す基準を自分なりに決めておくと良いでしょう。悩まずに捨てることができるかもしれません。自分のライフスタイルに合わせてルール化すると簡単です。
- 財布のレシートは毎週金曜日に整理する
- DMやチラシは部屋に入る前に破棄する
- 1年間読み返さなかった本は捨てる
- 2年以上着ていない服は誰かにあげるか処分する
保留もOK
人の感情というのは変わるので、時間経過とともに、悩むことなく捨てられるようになる場合があります。子どもに関連するものについては、時間が経って子どもが成長すると、捨てる判断がしやすいものがほとんどです。
なかなか捨てられないモノを段ボールに詰め込んで、押し入れの奥にしまいこんでいませんか?忘れた頃にその段ボールを発見したときも捨てるチャンスです。
残すのもアリ
楽しかった思い出は人生の宝物です。その楽しかった記憶と結びついたモノは安易に捨てないように注意してください。
記憶や感情に紐づいたモノは、捨てすぎると認知能力を低下させてしまいます。
特に50歳を過ぎたら、認知症を予防する観点からも捨てすぎに注意しましょう。ポジティブな記憶をよみがえらせるモノは、残しておいたほうがいいのです。