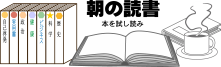※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
目次
はじめに
「失敗を誉める文化」や経済的に困窮しないセーフティーネットを会社に実装することと併せて、「CFO思考」を実践する個人が増え、「CFO思考」を持つ企業経営者が増えることで、日本経済は「血気と活力」を取り戻し、着実に成長への道に回帰できると考えています。
CFOが日頃対話している「海外投資家」は何を考えているのか、CFOの業務とはどういうものか「CFO思考」がなぜ企業や経済の成長につながるのかといったことを、具体的にお話していきます。
書籍情報
CFO思考
日本企業最大の「欠落」とその処方箋
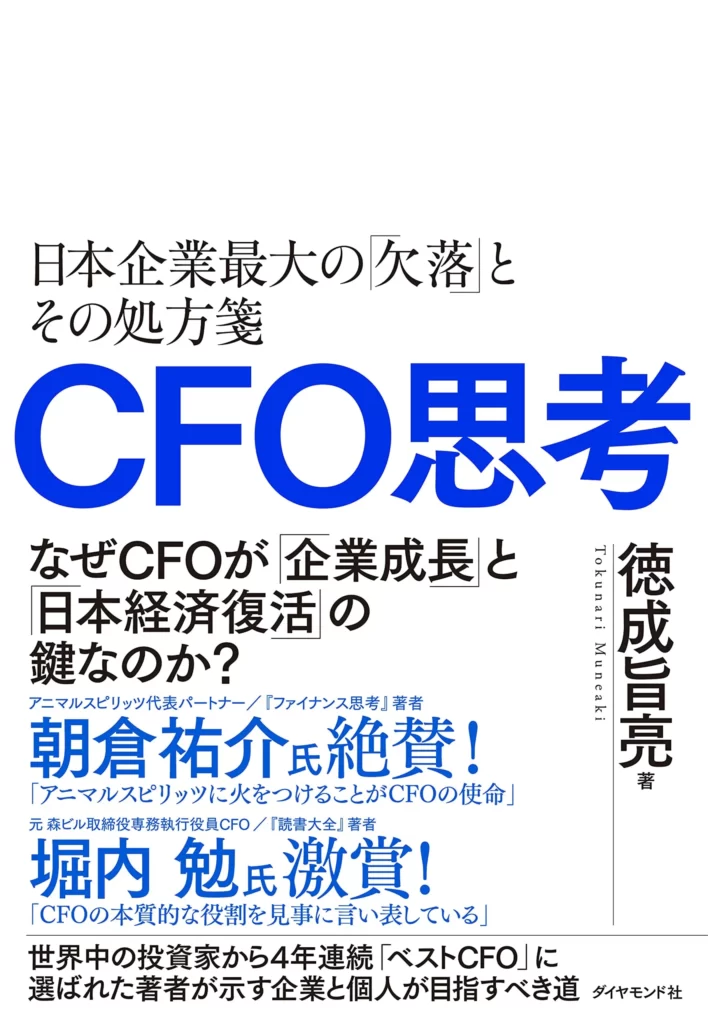
第1刷 2023年6月6日
発行 ダイヤモンド社
著者エージェント アップルシード・エージェンシー
装丁・図版・本文デザイン 遠藤陽一(DESIGN WORKSHOP JIN)
本文イラスト 德丸ゆう
DTP 桜井淳
校正 鷗来堂
製作進行 ダイヤモンド・グラフィック社
印刷 三松堂
製本 加藤製本
編集担当 上村晃大
ISBN 978-4-478-11804-7
総ページ数 349p
徳成旨亮
ニコン取締役専務執行役員CFO。
三菱UFJフィナンシャル・グループCFO(最高財務責任者)、米国ユニオンバンク取締役を経て現職。日本IR協議会元理事。
ダイヤモンド社
日本人の資産形成に貢献

作者: たなぼた
私がCFO時代にMUFGが行ったフィリピンやインドネシアなど東南アジアの「パートナーバンク」への出資や買収戦略は、「お客様とともに成長したい」という意思がその背景にあります。
多くの日本企業にとって、東南アジアは、自社製品を高品質でかつ安価に製造する生産拠点、あるいは自社製品の販売拡大先、2つの側面から重要な地域です。
お客様企業のアジア展開を支援するためには、現地通貨でのファイナンスや地場企業とバリューチェーンの構築のお手伝いなど、各国に根差したサービスが必須との考えがあります。MUFGは東南アジア各国の大手銀行への出資と戦略的提携を実行してきました。
資産運用戦略を採ったのは、資産運用業が金融業界のなかでも成長産業だからです。資産運用により得られる富は労働によって得られる富より成長が早いことがわかっています。また、日本国内の個人顧客への提供価値を高める狙いもありました。
少子超高齢社会で巨大な年金ファンドを持つ日本において、投資からのリターンを高めることは重要な社会課題です。資産運用業務の提供価値を高める活動の結果として、日本人の資産形成の役に立ちたいというのが、FSI買収の動機でした。
リスクを取らないことを叱る

Image by svklimkin from Pixabay
米国企業の取締役として異なる経験をしてきました。私が2020年まで取締役を務めていた米国のユニオンバンクの取締役会では、リスクをいかに取って、リターンを上げるのかが取締役会での議論の主要テーマのひとつだったのです。
「リスクアペタイト」という概念がリーマンショック後、銀行業界を中心に世界的に注目されるようになりました。事業戦略や財務計画を達成するために、リスクキャパシティの範囲内で進んで引き受けようとするリスクの種類と水準のことです。リスクに対して能動的に定義していくべきだとされています。
ライバル企業との関係や置かれている環境などを考慮してリスクの大きさを測ります。そのうえで、経営計画が十分に意欲的かどうかを議論することが、熱意が減ったとみられている日本企業に必要なのです。
その中心的役割をCFOが果たすべきだと考えています。
日本にはびこる「ルール疲れ」

Image by Nikolay Georgiev from Pixabay
ニューヨーク証券取引所の「立会場」にみられるような、資本主義のやる気を失わないための工夫は、言ってしまえば一種の無駄です。
意図的な無駄を行うためには、社会や経済や企業に「余裕」が必要です。「コンプライアンス疲れ」「ルール疲れ」を起こし、余裕が持てない状況に日本はあります。
日本人は、明治維新で郵便制度を英国から、民法をフランスから輸入してことかた、欧米で制定されたルールをバラバラに取り入れ、それらに真面目に従う習性があるのです。
外国製のルールが変更されると、後追いでフォローする必要があるのも負担を生みます。
「余裕」を生むには、リスクを取って手を抜くことです。内部管理においても「リスクとリターンの比較考量」という概念を入れることが有効です。
イベント一時間前に経営者ら時給の高い人々を集めて丁寧に事前の説明が行われる日本と、事前説明なく登壇させ、衆人環視のなかで鐘の鳴らし方と止め方をレクチャーする米国では、費用体効果が全く違います。
日本で生活水準を維持するために

Image by seung min lee from Pixabay
日本が世界経済のなかで埋没していく様子をみてきました。未来のある皆さまには、ご自身のキャリア形成と日本経済全体との関係について理解していただきたいと思います。
私の社会は、人口が微減していくなかで急速に65歳以上の人の割合が増えていく世の中です。どう考えても労働者が減少していくわけです。大量に移民を受け入れるなどをしないかぎりは避けることができません。
女性の積極的な労働参加や定年延長の施策をとっても、労働参加率の低下を鈍化されるだけで、減少していくのに変わりがないのです。
生活水準を維持するために必要な労働生産性を維持していく必要があります。自分の本分で自己実現を図り、それぞれの分野のプロとして「生産性」を高めていく努力をすることが必須なのです。
ビジネスパーソンがプロの人材となり、機会やデータを使って、高い生産性を上げることが今まで以上に求められます。
あとがき
CFOはテレビ東京でも特集を組まれるくらいに、注目を集める役職になりました。
異なる業種の上場企業2社でCFOを務め、日本企業に欠落しているものは、技術でも人材でもなく、経営者の計算と情熱だと感じています。
CFOが企業の成長エンジンとなり、CFO思考に基づいて日本経済が再び成長軌道に戻っていくと考えているのです。
感想
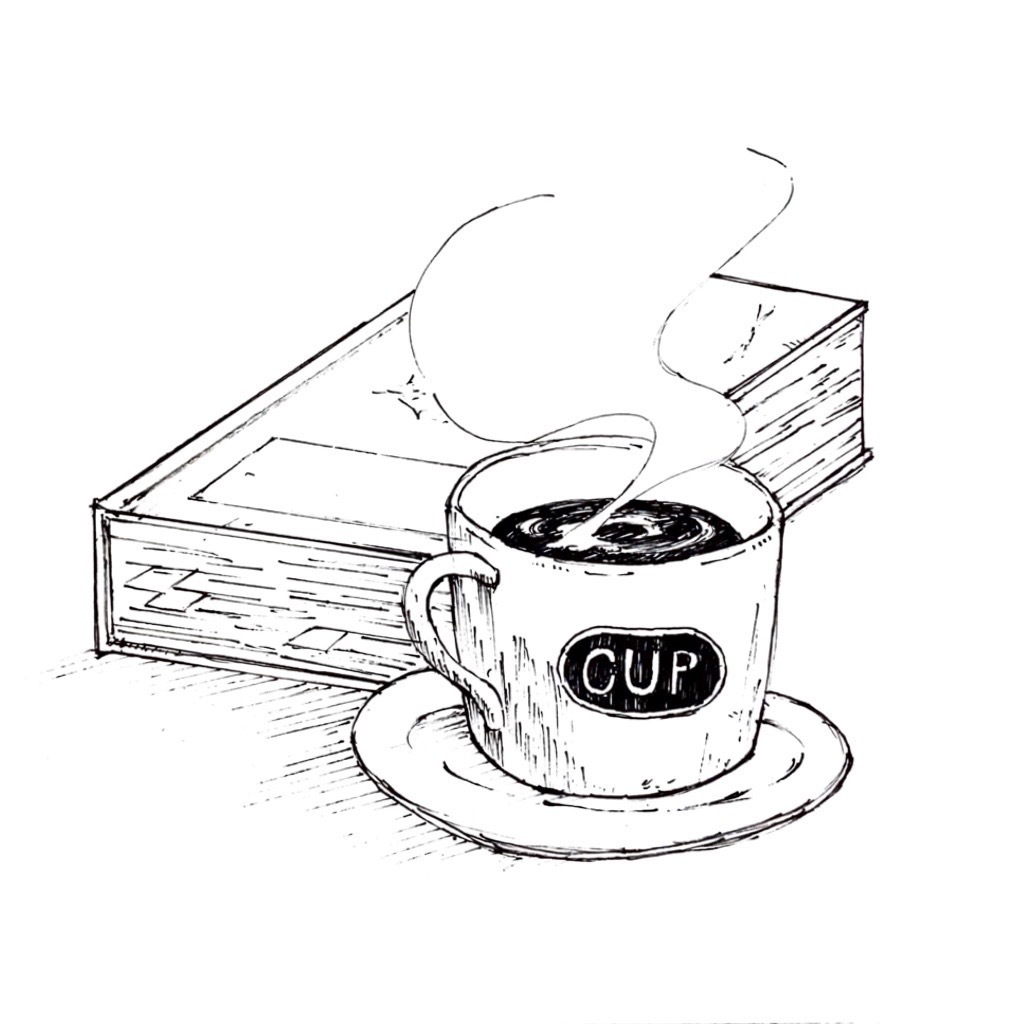
サイト管理人
経営者に計算能力と情熱が足りない。とんでもなくディスってます。
計画できないし、やる気もない。そんな経営者ばかりではないと思いたいです。
計画的にリスクをとって行動しようということなのでしょう、安全やどうでもいいルールなどを守ることに必死なってチャレンジできてないようにみえているみたいです。
財務などに加えてDXやリスクマネジメントなどをするのがCFOの仕事であり、日本の経営者には足りない部分だとの、少し具体的なことも書かれていたりもします。
事業がうまくいかない日本の起業家の処方箋となる書籍なのではないでしょうか。
下にリンクを貼っておきますので、本書の購入を検討してみて下さい。
購入リンク
紙

※amazonの商品リンクです。画像をクリックしてください。
電子

※amazonの商品リンクです。画像をクリックしてください。