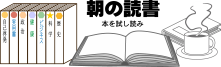※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
自動車用動力源の現状と未来
カーボンニュートラル時代に向けて

飯塚昭三
モータースポーツ専門誌「オートテクニック」創刊メンバー。取材を通じてモータースポーツに関わる一方、自らレースに参戦していた。編集者ドライバーのさきがけとなった。現在はフリーランスの編集者として、技術的観点から記事を執筆している。
グランプリ出版
- はじめに
- 序章 2050年カーボンニュートラルへ
- 日本の動き
- 世界の動き
- エンジン車禁止の方向性の裏にあるもの/9
- EVの有用性と弱点
- エンジンはなくせない、なくならない
- EVは小さいクルマ向き
- 第1章 自動車動力源とその課題
- 排気ガス規制とCO2排出規制
- CO2排出低減は燃費低減とイコール
- タンクtoホイールとウェルtoホイール
- ライフサイクルアセスメント (LCA)とは
- 第2章 高効率・ 低燃費エンジン技術
- ガソリンエンジン技術
- 可変バルブタイミング機構
- 切り替え式可変バルブタイミング (リフト) 機構
- 連続可変バルブリフト機構の基本原理
- 連続可変バルブリフトの効果
- いろいろな可変バルブリフトシステム
- 連続可変バルブリフトが広がらなかった訳
- EGR
- 気筒休止
- 1980年代からあった技術
- 近年の気筒休止技術
- マツダの例
- アトキンソンサイクル
- ミラーサイクル
- HCCI
- マツダのSPCCIとSKYACTIV-X
- 希薄燃焼 (リーンバーン)
- 副燃焼室方式
- 水噴射
- 可変圧縮比
- 可変圧縮の仕組み
- コンロッドが真っ直ぐ下がる
- 6気筒に近いバランス
- 高いEGR率
- e-POWER用ならではの特徴
- 2ストロークエンジン
- 発電用としてのロータリーエンジン
- 次世代2ストロークエンジン
- 対向ピストンエンジン
- 基本構造と作動
- 復活の要因
- ディーゼルエンジン技術
- 高圧多段噴射
- ディーゼルエンジン用触媒
- ハイブリッド技術
- ハイブリッドの分類と有用性
- ハイブリッドの分類
- ハイブリッドの有用性
- 2モーター式と1モーター式ハイブリッド
- 2モーター式ハイブリッド
- 1モーター式ハイブリッド
- ハイブリッドの分類と有用性
- 各社のハイブリッドシステム
- プラネタリーギヤを巧みに使ったトヨタのTHS
- 高効率を追求したホンダのe:HEV
- 三菱のPHEVシステムはシリーズパラレル
- シリーズ型のe-POWER/76
- ルノーのE-TECH ハイブリッド
- 代替燃料
- NG (天然ガス)
- LPG
- ガソリンエンジン技術
- 第3章 CO2排出ゼロの技術1 電池の現状と急速充電規格
- EV化の現状と課題
- 過剰なEV化とその鎮静
- EVの課題
- 電池の発明
- 電池の基本原理
- 鉛電池
- ニッケル水素電池
- リチウムイオン電池
- 全固体電池
- バイポーラ型蓄電池
- 金属空気電池
- 電池開発の現状
- 二次電池を巡る動き
- 充電の現状と展望
- 急速充電規格
- 欧米の巻き返し
- 電動車向け充電インフラ
- ワイヤレス充電 (非接触充電) 1
- ワイヤレス充電 (非接触充電) 2
- モーターの現状と展望
- モーターの損失
- 磁石
- ステーターコイル
- モーターの冷却
- インホイールモーター
- インバーターの進化
- e-Axle (eアクスル)
- EV化の現状と課題
- 第4章 CO2排出ゼロの技術 2 カーボンニュートラル燃料とエンジン
- バイオ燃料
- CO:を排出するバイオ燃料がなぜカーボンニュートラルか
- バイオ燃料の種類
- エタノール
- バイオディーゼル
- e-fuel
- e-fuel とはなにか
- e-fuelにはDAC (ダイレクトエアキャプチャー)が必要
- フィッシャー・トロプシュ法
- e-fuelの課題
- 水素燃料とその動力源
- 水素を使う意義
- 水素の燃料としての特徴
- 水素の種類
- 期待されるホワイト水素
- 水素の課題と現状
- 水素の安全性
- 世界は水素社会を目指している
- FCEV(燃料電池車)
- FCEVの歴史
- ベンツが火を付けたFC開発競争
- その後のFCEVの動向
- 海外におけるFCEV
- 今後を見すえて
- 水素エンジンの歴史
- トヨタの水素エンジンレース車の進化
- コンバージョン水素エンジンの可能性
- EVの限界とカーボンニュートラル燃料エンジン
- バイオ燃料
- 主要元素
- 主要分子
書籍紹介
著者の飯塚昭三さんは、長年にわたって自動車技術を取材してきたベテランのテクニカルライターです。東京電機大学で機械工学を学び、モータースポーツ専門誌の創刊に携わったり、自らレースに出場したりするなど、実践と理論の両方に精通した方です。そんな飯塚さんが、これまでの経験と知識を活かして、自動車の動力源がどのように変わってきたのか、そしてこれからどこへ向かうのかを丁寧に解説してくれています。
近代自動車について
この本の魅力は、まず現代の自動車産業が直面する課題をわかりやすく整理している点にあります。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンから、ハイブリッド、電気自動車、そして燃料電池車へと移行する流れの中で、それぞれの技術の強みや限界が具体的に書かれています。特に、カーボンニュートラルという大きな目標に向けて、どの動力源がどのように貢献できるのかが焦点です。環境問題への対応が急務となる中、技術的な視点だけでなく、社会や経済の動きも視野に入れた分析がされているのが印象的です。
今の技術をふまえて未来はどうなるかを予想
未来を見据えた話題も豊富で、例えば自動運転技術や新しいエネルギー源の可能性についても触れられています。今後、自動車が単なる移動手段を超えて、どのように私たちの生活や社会と結びついていくのか、そんな想像を膨らませてくれる内容になっています。飯塚さんの豊富な取材経験からくるリアルな視点が、未来予測に説得力を感じます。
日本の誇れる車産業のエンジンについて詳しく知れる
専門的な内容でありながら、図版を多用して視覚的に理解しやすい工夫がされています。エンジンやモーターの仕組み、バッテリーの構造など、普段なかなか触れることのないトピックも、図を見ながらだとぐっと身近に感じられます。自動車に詳しくない方でも、読み進めやすい配慮がされているのは嬉しいポイントです。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
EVは小さいクルマ向き

バッテリーのエネルギー密度はガソリンと比べてきわめて小さく、航続距離も長くできません。軽自動車は都市間の短距離走が多く、EVに向いていると判断できます。
軽自動車が輸出できるようになると、近所だけを運転するような人たちは軽自動車に乗り替えます。そうなると、海外の自動車メーカーの経営が傾いてしまうのが容易に予想できるため、軽自動車の輸出は規制されているが現状です。
なので、海外に少しでも輸出するために、ある程度の大きさをもった日産リーフという電気自動車が生まれました。
しかし、EVは長距離輸送が想定される大型トラックには向きません。大量のバッテリーを搭載しなければならず、積載スペースが確保できないという問題があります。ただし、配送ルートが決まっていて、充電スポットも確保されているような場合は、ある程度の大きさのEV化は可能です。
欧米は環境意識が高く、補助金の前提もあったため、テスラを始めとしたメーカーはEVに投資していました。超合金で硬く軽い外装の中にビッチリとバッテリーを搭載するといったもので注目を集め、国を巻き込んで商売をしていたのです。
しかし、大きなバッテリーを少数の車で使うより、小さなバッテリーを多数の車で使った方が環境負荷がかからず好ましいのは明らかです。大型のEVはかなり困難と言わなければなりません。その点、日産と三菱が軽自動車のEV、サクラとekクロスEVを2022年に発売したの理にかなっています。
マツダのエンジンの売り
ディーゼルエンジンでガソリンエンジン並みの燃焼効率を実現しただけでなく、ディーゼルエンジンの利点である圧縮着火をガソリンエンジンでほぼ実現させたのがマツダの凄さと言えます。HCCI技術と言われ「SKY ACTIV-X」を2019年に商品化し、車好きのなかで注目されました。
スパークプラグを補助的に使いことで、エンジン内の未燃ガスをさらに無くし、酸化窒素を出さず、燃焼効率を上げることに成功しています。未燃ガスを出さない希薄燃焼(HCCI)技術の理想に近づいており、今まで以上の熱効率向上を目指すなら欠かせない技術です。