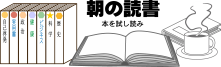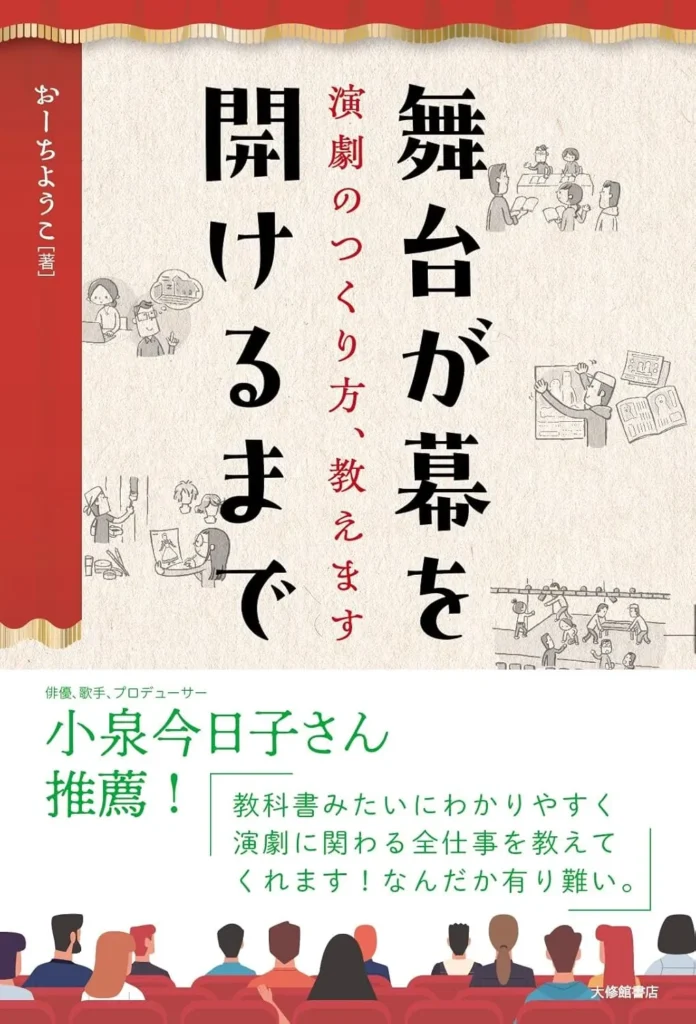※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
舞台が幕を開けるまで
演劇のつくり方、教えます
おーちようこ
フリーライター。
広告代理店を経て種版業界へ。20代に演劇と出会い、以後、舞台や本格ミステリなどの本を手がける。
大修館書店
- まえがき
- 絵で見る「舞台が幕を開けるまで」
- 鴻上尚史(作家・演出家)
- 相手の心を想像する心を育てる、それが演劇のすごさ
- 鴻上尚史(作家・演出家)
- 絵で見る「舞台が幕を開けるまで」
- 公演の企画
- 企画を立案する
- 岡村俊一(プロデューサー)
- 主演は決める、のではなく、決まるもの
- 早乙女太一(劇団座長)
- 昔の大衆に向けた演劇を、今の大衆に向けた演劇へ
- 岡村俊一(プロデューサー)
- 企画を立案する
- 脚本・演出の決定
- オリジナルの脚本を書く、あるいは原作から上演台本を書く
- 中島かずき(脚本家)
- 僕は例えるなら「注文住宅」なんです でも、予想外の家を建てることが楽しい
- 中島かずき(脚本家)
- 主演者と役を決める
- 脚本をもとに演出プランを立てる
- 石丸さち子(演出家)
- 演劇とは見知らぬ誰かと出会うこと
- 石丸さち子(演出家)
- オリジナルの脚本を書く、あるいは原作から上演台本を書く
- 公演の宣伝・チケット販売
- 宣伝材料/パブリシティを作成し、広く告知するために
- チケットを販売するために
- 関根明日子(制作)
- 稽古場で起きていることが舞台になる
- 関根明日子(制作)
- 演出計画の実現
- 作品世界にそった舞台美術の計画を立て、形にする
- 小林奈月(舞台美術家)
- 演出家が想像するその先へ
- 金安凌平(舞台監督)
- 「それはできない」と言いたくない
- 藤江修平(大道具製作)
- 舞台を通して人を心を豊かにする
- 黒澤花如(大道具製作)
- ひとつとして同じことがない仕事です
- 小林奈月(舞台美術家)
- 衣裳を借りる、あるいは作る
- 及川千春(舞台衣裳家)
- 衣裳が彩る世界観で作品によりそいたい
- 及川千春(舞台衣裳家)
- 作品世界に沿ったヘアメイクを考える
- 伊藤こず恵(ヘアメイク)
- このヘアメイクで役になれた、その言葉がうれしい
- 伊藤こず恵(ヘアメイク)
- 作品世界にそった舞台美術の計画を立て、形にする
- 稽古開始
- 稽古する
- 一色洋平(俳優)
- 舞台と客席にある透明な壁を破る、それが役者のおもしろさ
- 一色洋平(俳優)
- 証明プランを考える
- 松本大介(舞台照明家)
- 証明は角度の高さの芸術です
- 松本大介(舞台照明家)
- 音をつくる
- 佐藤こうじ(舞台音響家)
- その音は、いつ、どこで、誰のためになるのか
- 佐藤こうじ(舞台音響家)
- 稽古する
- 小屋入りから初日へ
- 本多愼一郎(劇場支配人)
- 劇場は真っ白であるべきです
- 建て込みをする
- 場当たり・ゲネプロをする
- 本番中
- 千穐楽を迎えて
- 本多愼一郎(劇場支配人)
- あとがき
書籍紹介
この本は、演劇が幕を開けるまでの裏側を丁寧に紐解いた一冊で、演劇に興味がある方なら誰もが楽しめる内容になっています。舞台のきらびやかな世界に目を奪われがちですが、その輝きがどのようにして生まれるのか、普段はあまり見えない部分にスポットライトを当てているのが特徴です。
公演の企画から始まり、脚本や演出の決定、宣伝やチケット販売、舞台美術や衣装の準備、そして稽古から初日を迎えるまでのプロセスが順を追って描かれています。第一線で活躍するプロデューサー、脚本家、舞台監督、衣装家など、演劇を支えるさまざまな職種の方々が登場し、彼らの仕事への思いや舞台への情熱が生き生きと語られています。たとえば、演出家が想像する世界をさらに広げる舞台美術家の工夫や、衣装が作品の世界観をどう彩るのかといった具体的なエピソードが、読む人の心をつかんで離しません。
演劇初心者の方にとっては、舞台がどのように作られていくのかを知る入門書としてぴったりですし、すでに演劇ファンである方には、普段見ている舞台の裏側をより深く理解するきっかけになるでしょう。観客として劇場に足を運ぶときの見方が少し変わるかもしれません。きらびやかな舞台の裏に隠された努力や情熱を感じながら、次に劇場を訪れるのが楽しみになる、そんな一冊です。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
企画を立案する

どの劇場で、どのくらいの期間、どんな演目を、誰が出演し、誰が演じ塚、といった内容を計画します。人気小説を舞台にしたい、若手俳優を名作古典に挑戦させたい、劇団旗揚げ公演など多種多様な企画があります。
企画の中心にいるのはプロデューサーです。公園の方針を決め、予算やスケジュールを管理し、全責任を負います。それらを実現するための業務を担うのが制作です。制作スタッフの仕事の範囲は幅広く、公演の全てに関わります。
作品にそった舞台美術を形にする

舞台上には、美術を考える美術家、その美術品を作る大道具、それを稽古場や劇場でまとめる舞台監督が演出空間や環境を作っていきます。
演出家の意向を汲み取り、演出空間の提案はもちろん、美術品の安全性も求められます。そのために、舞台上には客席から見えないところにさまざまな工夫と配慮がなされています。
また、地方公演がある場合は、セットを解体してトラックになどに積み込んで移動、運んだ先の劇場の大きさに合わせて再び組み立てる、といったことも想定して制作します。美術品の運搬や組み立て、安全性と各劇場での環境づくりなどの管理は、舞台監督の担当です。