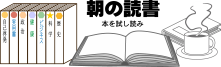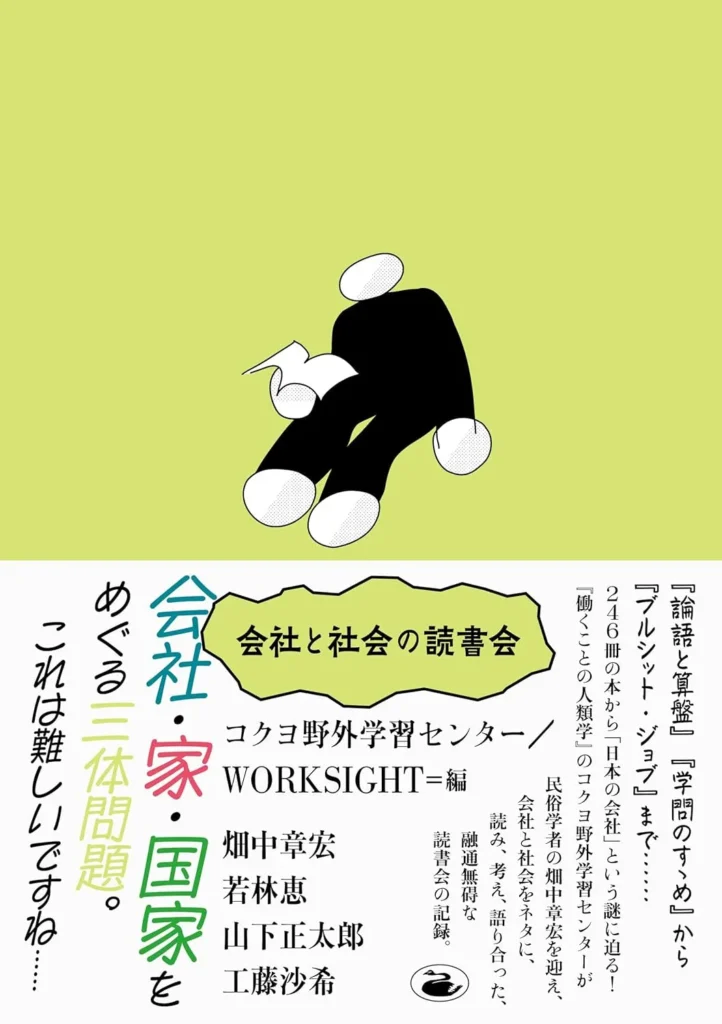※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
会社と社会の読書会
畑中章宏
若林恵
山下正太郎
工藤沙希
黒鳥社
- はじめに 会社を問う・社会をひらく 山下正太郎
- 第1回 会社がわからない
- 会社の民俗学
- 「会社=社会」だと思っていた
- 単数形としての「社会」
- メンバーシップの”タテ”と”ヨコ”商人はどこへ消えた
- 第2回 ふたつの「勤勉」
- 『論語と算盤』がわからない
- 資本主義の不気味な「精神」
- 貯める勤勉・働く勤勉
- 経営と温情主義
- 俸禄とへそくり
- 第3回 家と会社と女と男
- 女工から始まる
- 職業婦人・痴漢・ルッキズム
- 母性保護論争のあらまし
- 家はそもそも企業体
- 第4回 立身出世したいか
- 出世欲ある?
- 「立身」と武家社会
- 勉強して官僚になろう
- 暗記力がすべて
- 非凡なる凡人
- 第5回 何のための修養
- 社歌・社訓・創業者の胸像
- 松下幸之助の「わからなさ」
- ノン・エリートのための「修養」
- 新興企業に社葬が必要な理由
- トイレ掃除とジョブ・ディスクリプション
- 第6回 サラリーマンの欲望
- 研究者にも謎、当事者にも謎
- サラリーマンの絶望と欲望
- 転がる紙風船
- 第7回 会社は誰がために
- ChatGPTに仕事を奪われる
- ブルシット・ジョブがまた増える
- 仕事における「ケア」
- 「小商い」に戻る
- デジタル・プラットフォームと市場
- 結局会社は要るのか
- コラム 社会の補助線
- 遅刻してはいけない
- 虹・市・起業
- 速水融の「勤勉革命」
- 「失敗」や「挫折」を語れ
- 女性とアトツギ
- 経団連と自己啓発
- トーテムとしての「暖簾」
- 社宅住まいの切なさ
- 三菱一号館から始まる
- 「事務」はどこへ行くのか
- ブックリスト 本書で取り上げた本
書籍紹介
会社という存在が単なる働く場所ではなく、私たちの生活や価値観、欲望さえも形作る大きな力を持っていると気づかせてくれる点にあります。いつから「社会に出る」ことが「会社に入る」こととイコールになったのか。そんな問いから始まり、明治以降の日本社会がどのように会社という枠組みを消化してきたのかを、参加者たちが持ち寄った246冊もの本を通じて掘り下げていきます。
社会の異なるテーマ
それぞれ異なるテーマで展開されます。勤勉さとは何か、立身出世という夢の裏側、会社の中での男女の役割、そしてサラリーマンの欲望といった話題が、参加者の対話を通じて浮かび上がります。特に印象的なのは、専門家による一方的な講義ではなく、参加者一人ひとりが本を持ち寄り、自由に意見を交換する形式です。そのため、読んでいるとまるで自分もその場にいて、議論に加わっているような気分になります。
漠然とした不安の整理に
この本は、ビジネスパーソンだけでなく、会社や社会との関わり方を改めて見つめたいすべての人におすすめです。通勤電車の中でページをめくりながら、自分にとっての「会社」とは何か、「社会」とは何か、じっくり考えてみるのもいいかもしれません。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
貯める勤勉・働く勤勉

資本主義を規定する要件は「個人による資本の私有」ということです。資本とは、生産のための土地、資金、施設、設備のことをさします。
資本主義になる以前の日本では、商家が資本と呼べるものは「家」でした。資本主義とそれ以前では、ここの財に違いがあります。
ヴェーバーによれば、資本主義の蓄財思考は宗教から生まれたとのことです。ジャン・ウェスレーという宗教家は「すべてのキリスト者にたいして、できるかぎり多くの利益を獲得するとともに、できるかぎり節約するように戒めねばならない。しかしその結果はどうなるかというと、富が蓄積されるということなのだ。」と述べており、ヴェーバーはこの考えに資本主義が帰結しているのではないかと考えたようです。
宗教が勤勉・節約を促し、富みが増すと宗教が薄まり現世への執着が高まって、現代の同等性や倫理観を帯びていったという主張ともとれます。その資本主義の成立の経緯があったと考えると、日本の場合は、目に見える価値軸としての「勤労」という概念を手掛かりにするしかなく、結果として、精神力が必要な「節約」が抜け落ちて「勤労」だけが残っていったと言えるでしょう。