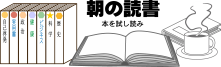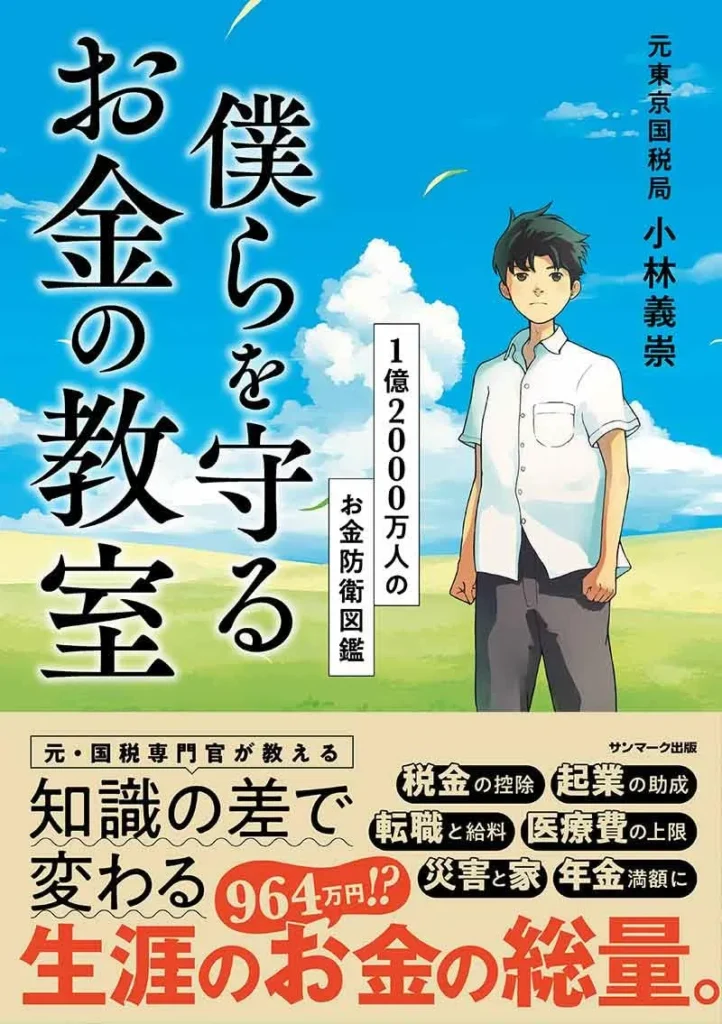※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
僕らを守るお金の教室
小林義崇
元国税専門官、フリーランスライター、Y-MARK 合同会社代表。
一般社団法人かぶきライフサポート理事。
相続税の調査や所得税の確定申告の対応に従事し、2017年にフリーライターに転身。
サンマーク出版
- はじめに お金は減っても気づかない?
- 「知」は盾でありカ―投資を考えている人も、そうでない人も
- 知るだけで「税金」が「還付金」に
- 独立初年から「節税・数十万円」「保険料引き下げ」に成功
- 0章 僕らの世界にただようお金
- お金を守るすべは「ライフステージ」ごとにある
- なぜ「お金の悩み」は尽きないのか?
- 資産家は「あらかじめ」貯金する
- 先取り貯金で「月10万円」貯まる
- 「2万人」がお金をもらい損ねた話
- 「教育費は子ども1人1500万円」は本当?
- 支援制度の3タイプを使いわける
- 節税コラム1 節税とは「公平」を自分でつかむ手段
- 1章 人の誕生
- 出産で最大「50万円」もらえる出産育児一時金:
- 「パートナー」「家族」の出産でも受給できる
- 「おむつ」「ミルク」ギフトがもらえる出産・子育て応援交付金
- 産休・育休中も収入8割キープ出産手当金・育休手当
- 1週間分の「出産手当金」/産後8週間以降で「育休手当」
- 育休復帰時、忘れちゃいけない手続き標準報酬の特例措置
- 育休復帰後・忘れないで!手続き 社会保険料を下げる「2書類」/育休復帰後・忘れないで!手続きの将来の年金を守る「申出書」
- 子どもの「病院代」は基本ゼロ 乳幼児医療費助成・子ども医療費助成
- ・子育て中のもっとも強い味方 児童手当
- ひとり親障害のあるお子さんの家庭への支給
- 節税コラム2 産休・育休のパートナーを「扶養」に入れる
- 配偶者控除—「103万円」の壁/配偶者特別控除「150万円」の壁
- 出産で最大「50万円」もらえる出産育児一時金:
- 2章 教育
- 3~5歳は無償で保育所へ通える
- 保育園・幼稚園、無償化のルール/幼稚園の預かり保育支援
- チリツモな学用品・給食費を援助 就学援助制度
- 私立中学校は年間学費「144万円」
- 「私立」でも支援金で公立並みの授業料に高等学校等就学支援金
- 「私立=お金が心配」と思ったら私立高等学校等授業料軽減助成
- 高校入学金で困ったら貸与型奨学金
- 大学の授業料は「多子世帯」無料に――ただし数え方に注意
- 奨学金は「シミュレーション」する大学生の教育費への備え
- お金がなくても「留学」したい海外留学支援制度
- 節税コラム3 税金がかからない投資「新NISA」
- NISAのしくみ/新NISAの始めかた
- 3~5歳は無償で保育所へ通える
- 3章 仕事
- 税金は基本「多め」に取られる
- 「控除」ってなんですか?/「年末調整」とは?
- やらない手はない「確定申告」
- 「ふるさと納税」で税金を減らして返礼品もゲット
- 「返礼品」のお得度を調べる方法
- 退職後、収入がゼロになると思うと不安です..
- 転職、独立起業の支え
- 「雇用保険」ってなんですか?
- ・会社を辞めても「収入ゼロ」にならない失業手当
- 自己都合退職のルール「2か月は給付に制限」
- 早めに転職先が決まれば「手当」あり―再就職手当、就業促進定着手当
- 再就職手当/就業促進定着手当/就業手当
- 「スキルアップ」しながらお金がもらえる 教育訓練給付
- 「独立」「起業」への挑戦を応援―創業助成金・公庫融資
- 創業時の経費を給付する「創業助成金」オフィス賃貸料も!?/起業時、実績がなくても「融資」を受けられる/「開業費」で税金を圧縮
- 自分で事業するなら「青色申告」で
- 年金が払えなくなったら必ず「免除」「猶予」を
- 20万円の未納で60万円の損に/国民年金の免除/国民年金の「納付猶予制度」
- 退職時、健康保険を「任意継続」する
- 節税コラム4 iDeCoで節税しながら「退職金」を増やす
- iDeCoとは?/iDeCoでも「退職所得控除」が使える
- 税金は基本「多め」に取られる
- 4章 住まい
- 「10年以上のローン」で家を買い年間2万円節税住宅ローン減税
- 省エネならもっと減税!
- みんな「省エネ」に殺到人気でストップした施策も
- 省エネ住宅・新築で最大「100万円」子育てエコホーム支援事業 ・「窓」を変えて助成金!
- 先進的窓リノベ事業
- 給湯器を安く手に入れ電気代も下げる給湯省エネ事業
- 変動 固定? 住宅ローンで得するのはどっ
- 「災害」で家が壊れたら 耐震診断費用助成・被災者生活再建支援制度
- 節税コラム5 家購入時、「贈与税」が 家購入時、「贈与税」がかかる人・かからない人
- 親から援助を受けたら
- 「10年以上のローン」で家を買い年間2万円節税住宅ローン減税
- 5章 病気・ケガ
- 老後病院の自己負担額には「上限」がある
- 入るべき保険・いらない保険
- 100万円の医療費が「8万7千円」に――高額療養費
- 8万7千円→4万4千円にさらに下がる?!?!
- 仕事を長く休んでも「収入」を維持傷病手当金・労災保険・介護休業給付
- 4日以上仕事復帰できないとき「傷病手当金」/「労災がおりる」とどうなる?/
- 「親の介護」で仕事をしばらく離れる
- 「後遺症」を負った後の生活を支える障害年金
- 障害基礎年金/障害厚生年金
- 節税コラム6 「医療費」は確定申告すれば節税になる
- 「ドラッグストア」でも節税!?
- 6章 老後
- 老後、毎月「5万5千円」不足?
- あなたがもらえる「年金」はどれ?
- 年金は申請しないともらえない
- 未納の確認は「35歳」「4歲」「30歳」で届く封書で/ねんきんネットで「自分の年金」を確認/「役職定年」で年金が下がることも
- 年金は「現役世代の収入」の50%ルール
- 早期退職で「年間3万円」年金が減る!?!?!?!
- 年金でも「節税」できる確定申告不要制度
- 老後でも年金は増やせる国民年金の任意加入
- 「会社勤め」で年金を増やせる人加給年金・振替加算
- 年金は「受け取り時期」で額が変わる年金繰り下げ受給
- 年金額が最大になる「繰り下げタイミング」
- 働きながら年金をもらう在職老齢年金
- 年金が減る「働き方」
- 65歳以降の「転職活動」でもらえる高年齢求職者給付金
- 同じ会社で「再雇用」も支援あり高年齢雇用継続給付……
- 60歳時の給料の「15%未満」だともらえる給付金/他社に再就職、給料が15%未満だともらえる給付金
- 「退職金」の上手な受け取り方
- 38年1日は「39年」とカウント
- 医療費の自己負担が「2割」に高齢者医療制度
- 介護サービス利用料は「9割」補助—介護保険
- 介護費の自己負担を下げる 「世帯分離」
- 介護施設の「食事代」まで補助されるケースも
- 「死亡後」に遺族が受け取れるお金 死亡一時金・埋葬料
- 死後の家族の生活を支える遺族年金・
- フリーランス(国民年金第1号被保険者)が亡くなった場合/会社員(国民年金第2号被保険者)が亡くなった場合
- 節税コラム7 「相続税」がかかる人・かからない人
- 相続を受ける準備
- 円安・インフレ・マイナス金利解除―これからのお金の展望
- おわりに お金の支援を築いた先人たち
書籍紹介
元国税専門官という経歴を持ち、東京国税局で相続税や所得税の仕事を長年経験してきたお金のプロです。その豊富な知識を活かして、普段私たちが気づかないようなお金の落とし穴や、賢く生きるためのヒントを丁寧に解説してくれています。
誰でも理解できるように
税金の仕組みや保険の選び方、老後の資金計画など、人生のあらゆる場面で必要なお金の話が網羅されています。特に「知らないと払いすぎたり、もらい損ねたりする」という視点が印象的で、読んでいると「こんなことも知っておくべきだったんだ」と気づかされる瞬間が何度もあります。小林さんの実体験や具体的なエピソードが織り込まれているので、ただの知識の羅列ではなく、身近に感じられる内容になっています。
お金で生活が守られる
「お金に守られる人生」を送るための指南書でもあります。生涯のお金が1千万円も変わるかもしれないという言葉にドキッとしますが、それだけ私たちの選択次第で未来が変わるということです。読後には、お金の管理に対する意識がぐっと高まり、日々の生活の中でちょっとした工夫をしてみようと思えるはずです。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
お金を守るすべは「ライフステージ」ごとにある

「払う必要のないお金を払わない」「もらえるはずのお金をきちんともらう」この2つは徹底しましょう。これに勝るお金防衛術はありません。この2つのことは、よく漏れていることが多いのです。
お金の支援に関する手続きは数が多く、地方自治体によっても名前が違うことや分かりにくく複雑です。簡単にできないようにはできています。それを、丁寧に知らせてくれる人はいません。日々いそがしいなか、自分に関係することに限ったとしても、お金の知識をくまなく知っている自身があるでしょうか。
情報が多すぎるなか、混乱をさけるコツは「お金を守るすべはライフステージごとにある」という意識です。
「子どもが高校生になると使える制度があったような」と思い出すだけのお金防衛術なら、その時々に使える支援制度の見逃しを防げます。
21世紀を生きる私たちが知っておきたいキーワードは、「子育て」「多様な働き方」「省エネ」です。このキーワードを実践する人への国の支援が手厚くなる見込みが大きいということを頭の片隅に置いておきましょう。
いらない保険

日本に住むほぼ全員が何らかの公的医療保険に加入しています。治療費が知らずのうちに安くなっているのです。大きく分けると「健康保険」と「国民健康保険」の2つの公的医療保険があります。会社員が加入するのが健康保険です。
大手企業は「健康保険組合」、中小企業は「全国健康保険協会(教会けんぽ)」の健康保険から医療費などの補助を受けられます。自営業者、学生、無職の人は「国民健康保険」に加入します。
健康保険の強みは、扶養家族まで医療費をカバーしてくれる点です。国民健康保険の場合、家族全員の所得に応じて1人ずつ国民健康保険料が算定され、合算した額を世帯主が負担するため、家族が多いほど保険料が増えます。また、健康保険には「出産手当金」や「傷病手当金」が給付される制度があります。
国民健康保険の場合は、給付が受け取れない場合が多く、特に子どもが小さかったり稼ぐ能力が無かったりする場合には、民間の医療保険に加入することもあるでしょう。
公的医療保険でカバーできないリスクには、民間の保険に入る必要性があります。「自動車保険」の物損、対人賠償の無制限など、自賠責保険では限度がある保障に、もしもの備えをしましょう。他に民間の保険で入る意味があるものは、「地震保険」です。地震によって火災が起きても火災保険では保障されません。起きる確率の高く被害の大きい災害に保険で補うのも、望ましいことです。ネットの保険であれば、保険料が抑えられるので、そこも意識して調べましょう。