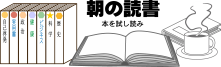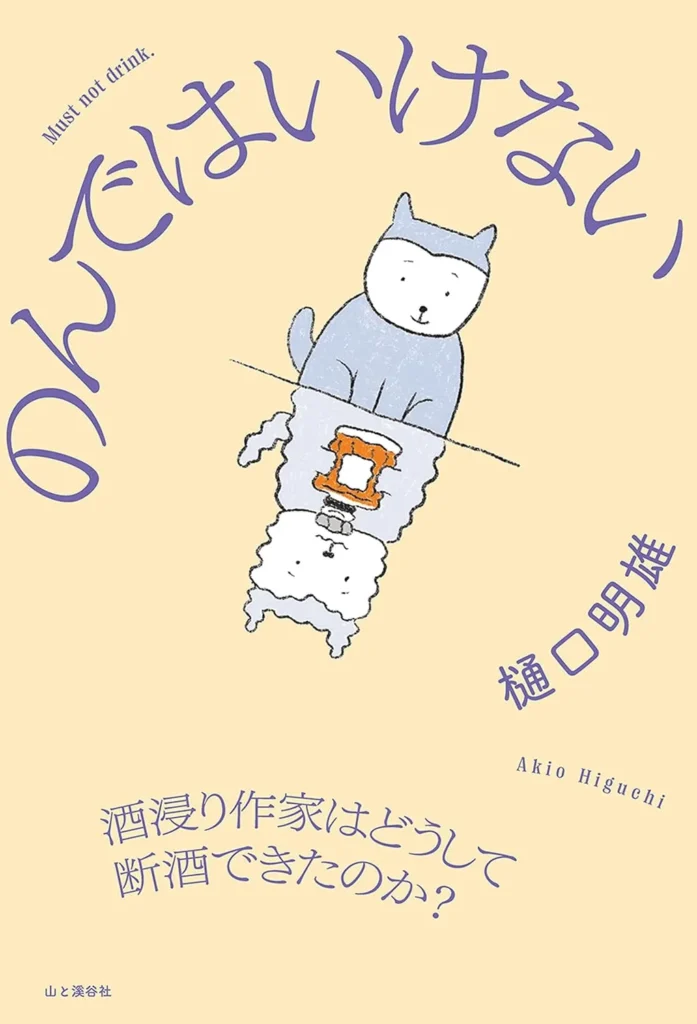※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。
目次
書籍情報
のんではいけない
酒浸り作家はどうして断酒できたのか?
樋口明雄
フリーライターなどを経たのち、ライトノベル作家としてデビュー。
山と溪谷社
- はじめに
- chapter1 都会で呑む
- chapter2 山で呑む
- chapter3 酒を断つ!
- chapter4 前向きに生きる!
- おわりに
書籍紹介
酒に溺れていた作家がどのようにして断酒に至ったかという、ドラマチックな人生の変遷を描いています。
著者の体験談
この書籍は樋口明雄自身の経験に基づいており、酒を愛し、酒に依存していた彼がどうしてその生活から抜け出すことを決意したのかを深く掘り下げています。物語は東京の阿佐ヶ谷時代から始まり、彼が酒に溺れていたあの時代を生き生きと描写します。そこでは、愛すべき人々との出会いや交流が豊かに語られ、読者は作家の日常を垣間見ることができます。
ストーリー概要
山梨県に移住した時期が描かれます。都会から離れた場所でも酒に溺れる彼の姿が示され、田舎での生活が彼の飲酒習慣にどのように影響を与えたかが考察されています。この部分では、移住者ならではの視点から自らの生活を見つめ直す彼の姿が浮かび上がります。
物語の核心は第3章で明らかになります。ここでは、樋口が断酒を決意するきっかけや、その後の孤独との闘いが描かれます。彼の内面の葛藤や、酒を手放すことへの恐怖、それでも一歩踏み出そうとする勇気がリアルに伝わってきます
最終章では、断酒の効果が軽やかな筆致で語られます。酒に依存しない生活がどれほど彼の創作活動や日常生活に影響を与えたのか、読者はその変化を追体験することができます。この部分は特に、酒を断つことで得られる自由や新たな視点について深く考えさせられます。
人生の岐路に立つ人へ
断酒の話ではなく、人生の転機や自己改革の物語でもあります。酒に溺れる作家が、自身に課した「断酒」という大改造を経て、どのようにして新たな自分を見つけたのか。その過程は、読者に希望や勇気を与えるものです。
ユーモアと哀愁を交えながらも、時に鋭く自己批判的であり、非常に人間味あふれるものです。『のんではいけない』は、酒にまつわる問題を抱える人々だけでなく、人生の岐路に立つすべての人々に読んでもらいたい一冊です。
試し読み
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
山呑み

田舎暮らしでの酒の飲み方に、焚火をしながら飲むということがありました。
地方移住をして庭に焚火場を作ったのはそのためです。焚火をしながら、缶ビールや酎ハイ、バーボンをお湯割りやロックアイスで飲みます。ゆらゆらと揺れる炎を見ながら飲み続けるといった具合です。
気分良く仲間内でお酒を楽しんでいると、酔いが進みます。酩酊したあげく、千鳥足で歩く者、尻餅をつく者、川に落ちる者もいました。私も何度か醜態をさらしています。
健康の実感
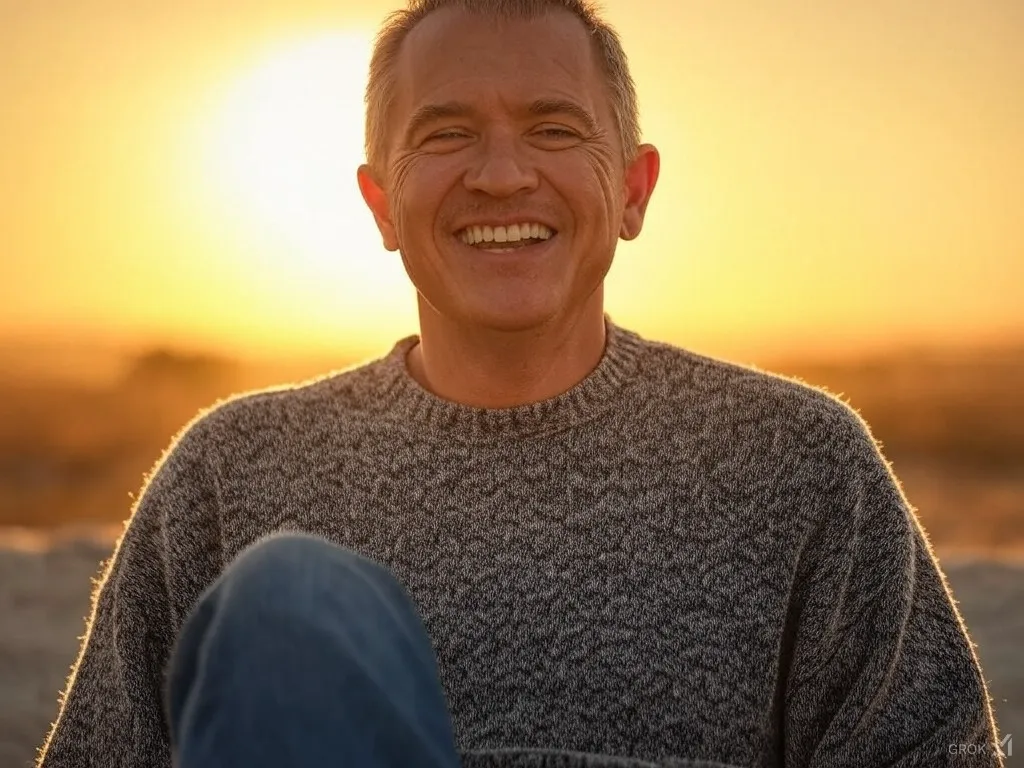
朝、目を覚ました時、宿酔いという悩みの種からすっかり解放されました。
「深酒をしてしまった」と重たい頭を抱えて後悔し、がっくりと落ち込むことがいっさいなくなっています。「もう酒はやめる」という戯言も言わなくなりました。
毎日をアルコールを摂取することは、肝臓や腎臓に負担をかけ、生活習慣病や癌の原因をせっせと作り、ストレス負荷をかけ続けて、脳細胞を死滅させています。
深い睡眠のときに脳内に溜まった疲労物質が除去できないことがわかっています。飲酒直後は眠たくなるものの、アルコールが体内で分解されアセトアルデヒドが生成されると、このアセトアルデヒドは覚醒作用をもたらします。数時間後に覚醒作用が発生するので、寝酒をすると確実に熟睡できません。
中国の新王朝の皇帝が、アルコールが消毒作用があることから、「酒は百薬の長」と国民を騙して酒税を取った事実があります。この国民を騙す『漢書』「食貨志」を揶揄して日本に広めたのが『徒然草』です。